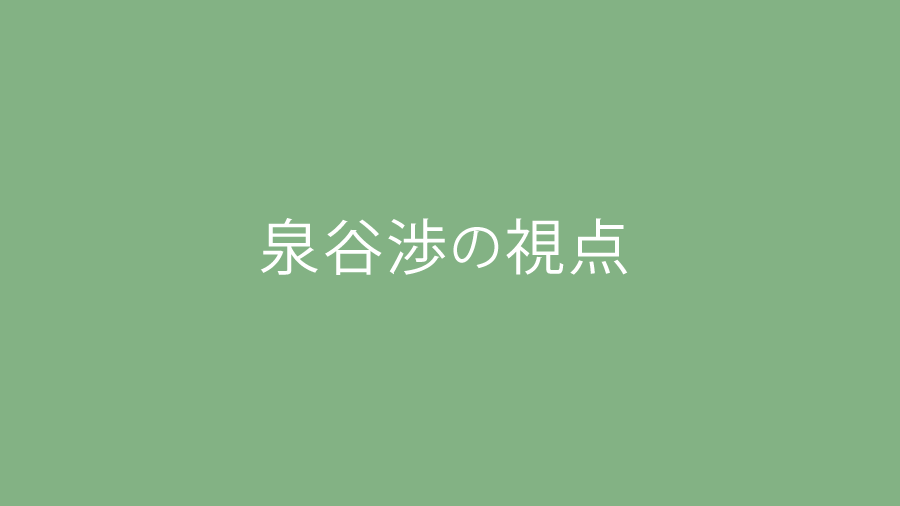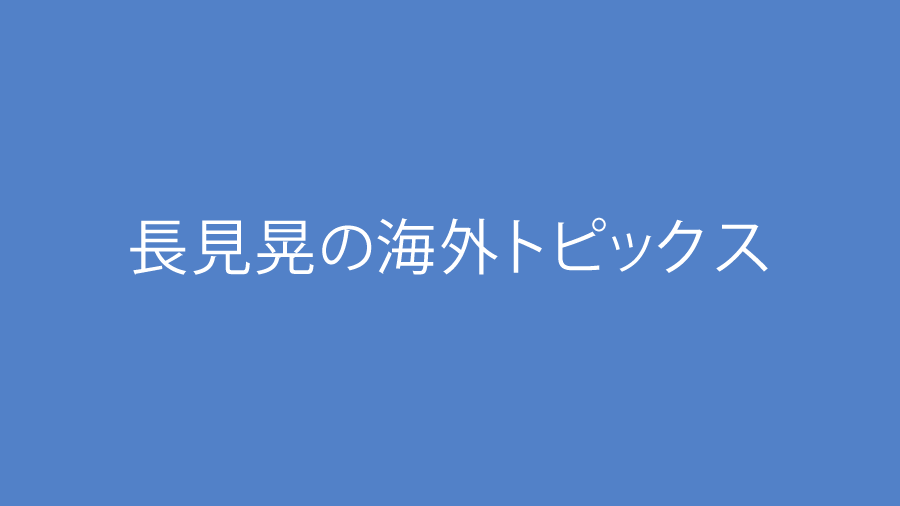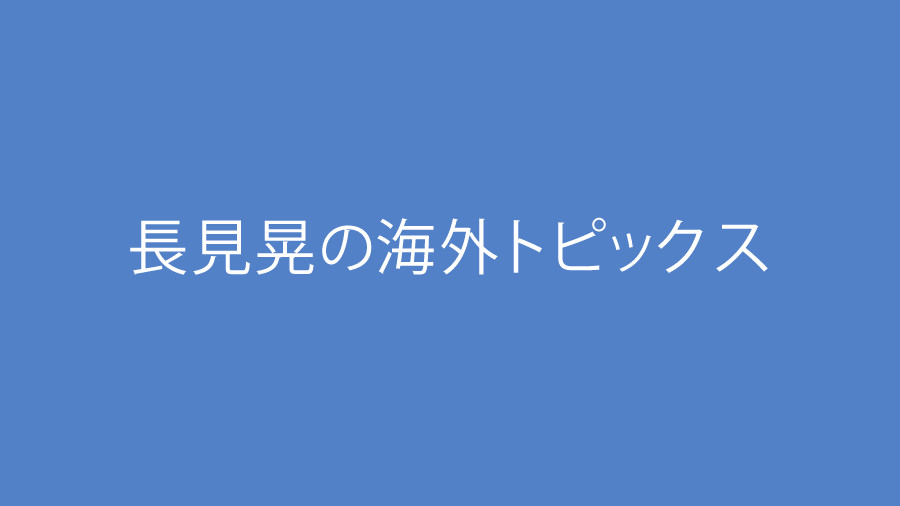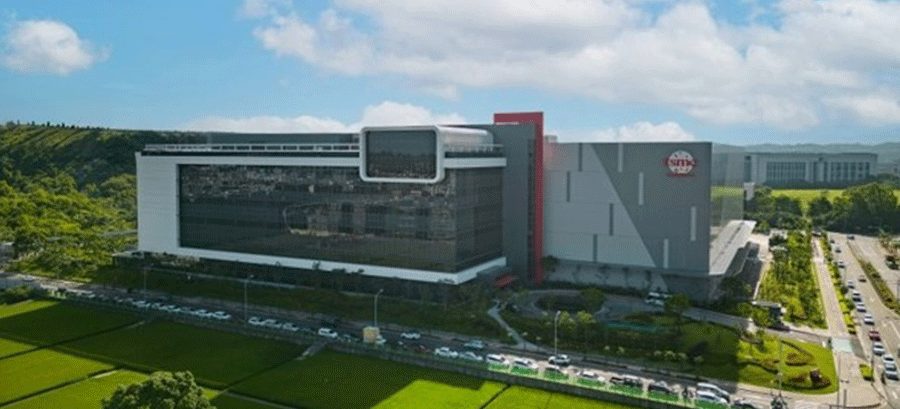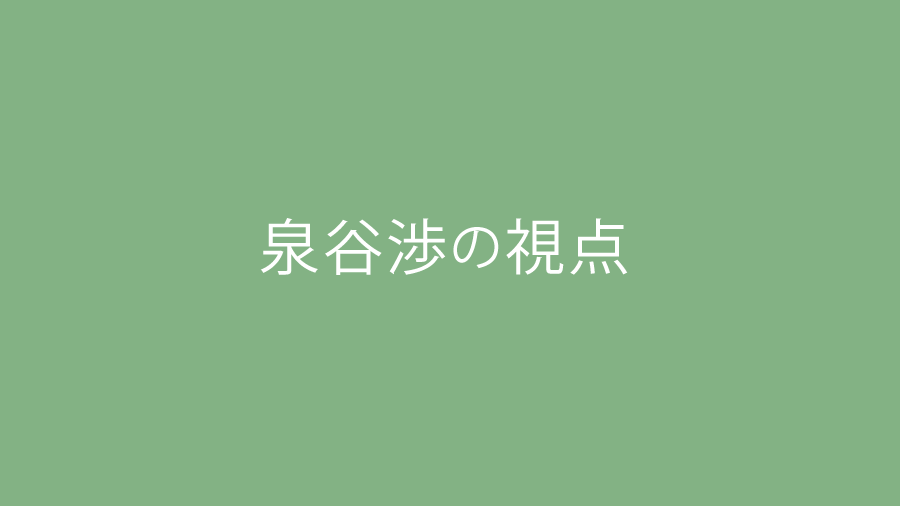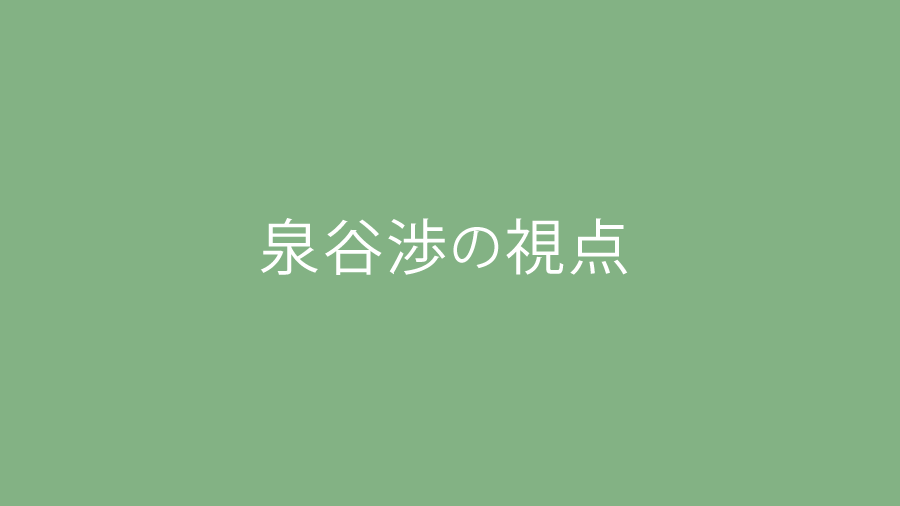
2024年2月 6日
|泉谷渉の視点
2024年の半導体市況については、さまざまな意見が取り沙汰されている。世界最大の半導体消費市場である中国経済の低迷、さらには新型コロナウイルスからの復興の遅れなどを理由にネガティブな見方をする人たちが多い。しかし超ポジティブの立場をとる筆者は決してそうは考えない。結論を先に言えば、2024年の世界半導体生産額は前年比15%増を達成すると見ており、90兆円の大台乗せも十分にあり得ると考えているのだ。
[→続きを読む]
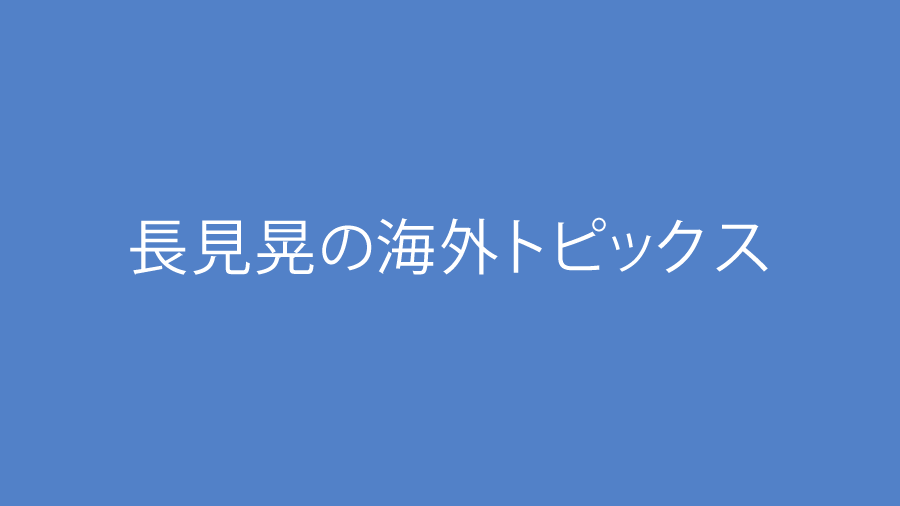
2024年2月 5日
|長見晃の海外トピックス
米国国内の半導体製造強化、および主として米中摩擦からくる米国の輸出規制は表裏一体を成す安全保障に向けた戦略的な取り組みであるが、前者の米国「チップス法」による補助金交付を巡る動きが依然目につく一方、対中国を意識した規制のさらなる動きが並行している現時点である。補助金の配分がなかなか決まらないとして、インテルはオハイオ州での工場建設を遅らせる動きが見られている。また、米国の半導体装置輸出規制は「公平な競争条件」を確保する上で見直しが必要、と米国・SIAが米国政府に求めている。
国内の半導体製造強化に向けて国内外各社に補助金を配分していく段取りの一方で、輸出規制強化の施し具合に追われる現状が見え隠れしている。
[→続きを読む]
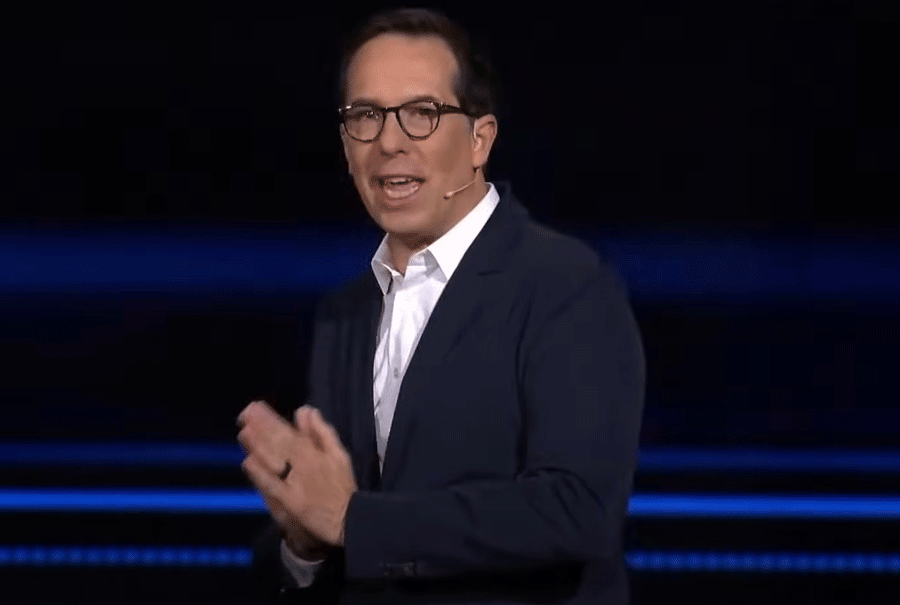
2024年2月 5日
|津田建二の取材手帳
2024年の半導体産業はどうなるのだろうか。ここ数年、新型コロナに振り回され、やっと落ち着きを取り戻すようになってきた。2020年はじめに新型コロナパンデミックが日本でも現れ、工場や企業の一時休業やロックダウンなどにより生産計画が狂ってしまった半導体業界。その後すぐに強い需要がやってきて、生産するも半導体不足が長く続いた。流通関係を中心に二重、三重の発注が続いたかと思うと、今度は一転、在庫が溜まりすぎて需要が落ち込む状況が22年後半から23年にかけて続いてきた。
[→続きを読む]

2024年1月30日
|服部毅のエンジニア論点
台TSMCは、去る1月18日に2023年第4四半期の決算説明会(台積公司法人説明会、図1)でCFO による同四半期の業績説明(参考資料1)に続いて、同社CEOの魏哲家(C.C. Wei)氏と同社会長の劉徳音(Mark Liu)氏は、機関投資家(世界的に有名な証券会社や投資銀行など)の多種多様な質問に即答した。
[→続きを読む]
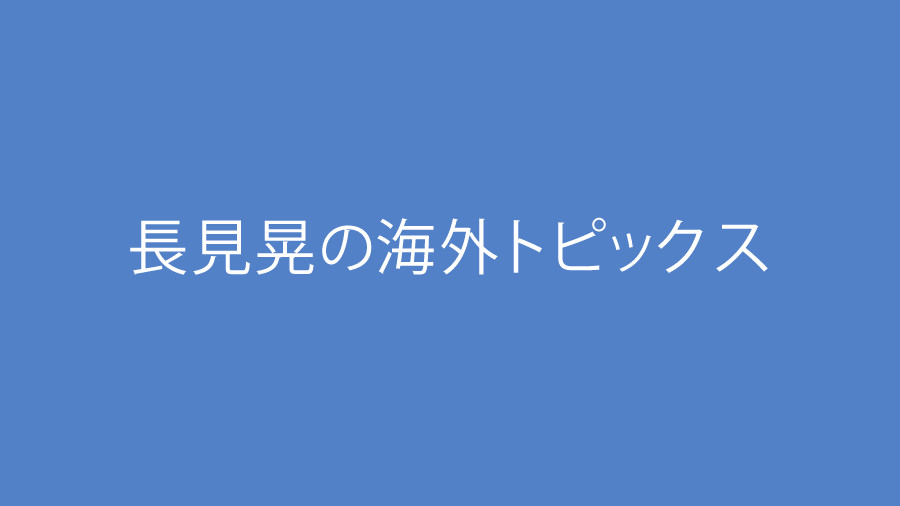
2024年1月29日
|長見晃の海外トピックス
AI(人工知能)分野を巡る様々な動きに引き続き注目させられている。
MicrosoftとオープンAIの連携が進む一方では、米連邦取引委員会(FTC)は公正な競争を損なわないか調べる構えである。AI半導体関連では、牽引するNvidiaに加えて、AI向けHBM3メモリが好調のSK Hynixが2023年第四四半期に久しぶりに黒字に戻している。インテル、TI、STMicroなどは本格回復には至っておらず、AI関連が業績を大きく引っ張る現状を映し出している。TSMCはAI半導体関連の押上げで本年20%の伸びを見込んでいる。AI重点化への再構築で、人員削減の動きも見られるなど、激動を伴う当面の様相含みである。関連各社の取り組み、および今後への見方の内容を取り出している。
[→続きを読む]

2024年1月22日
|長見晃の海外トピックス
半導体各社の業績発表でもAI(人工知能)需要による売上げ伸長が見込まれ、TSMCは本年20%増を見込むとの発表が行われている。年初早々半導体関連の大型M&A(企業の合併・買収)が2件報じられ、Hewlett Packard Enterprise(HPE)がJuniper Networksを、そしてSysnopsysがAnsysを、ともにAI需要の拡大への技術対応が説明されている。次に、米国政府がCHIPS and Science Actにより設立したNational Semiconductor Technology Center(NSTC)を運営するために設立されたNational Center for the Advancement of Semiconductor Technology(Natcast)が発表され、注目している。大統領選挙に向け、半導体に焦点が当てられる中、今後の半導体開発の方向性が問われていく。
[→続きを読む]

2024年1月15日
|長見晃の海外トピックス
米国・Semiconductor Industry Association(SIA)より月次世界半導体販売高が発表され、昨年11月について$48.0 billionで、前月比2.9%増と9ケ月連続の増加、そして前年同月比5.3%増と1年3ヶ月ぶりのプラスとなっている。年間販売高最高の2022年では$50 billion台の月次販売高が続いており、人工知能(AI)はじめ引っ張る需要の本格増大が待たれるところである。年初恒例の世界最大のテクノロジー見本市「Consumer Electronics Show(CES)」が1月9-12日、Las Vegasで開催され、「AI」「モビリティー」を主テーマとして多彩な展示が繰り広げられている。全体概況、そして半導体各社の取り組む技術、製品および戦略関連の内容を取り出して分類している。
[→続きを読む]
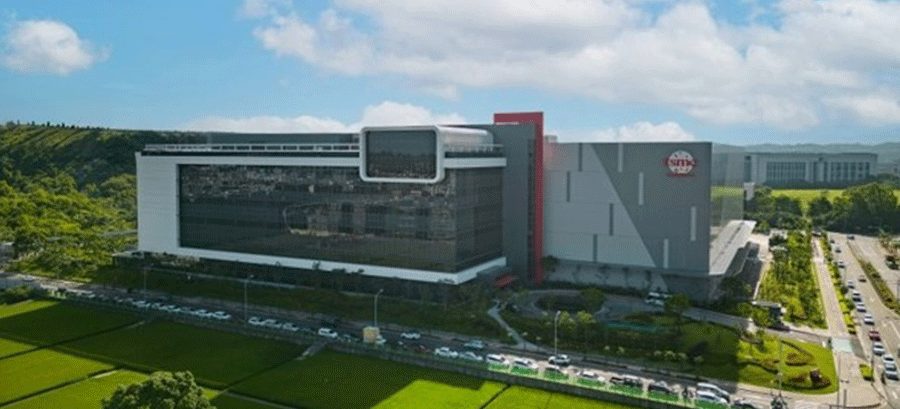
2024年1月12日
|服部毅のエンジニア論点
前回のブログ(参考資料1)で、TSMCの台湾域内だけではなくグローバルなファブ一覧を示したが、実はこれがTSMCのファブのすべてではない。前回紹介したのは、前工程(Frontend、ウェーハプロセス工程)のファブだけであって、実は「先進的な後工程」(先進アッセンブリと最終テスト)のファブが以下のように台湾内の5ヵ所に点在している。これらの既存ファブとは別に今後さらに2つのファブを増設する見込みである。
[→続きを読む]

2024年1月 9日
|長見晃の海外トピックス
能登半島地震、航空機衝突事故と非常に多難な新年のスタートとなった我が国である。半導体業界におけるこの年末および年始における動き&見方として、3点に注目している。本格的な市場回復のなるべく早い期待が強まる一途の中、裏づけるデータが引き続き見られるとともに、期待製品の打ち上げが行われようとしている。次に、米国国内の半導体製造強化に向けたCHIPS and Science Actによる米国政府の補助金支給が、Microchip社に対して行われている。米国での半導体工場建設を進めている各社への支給が、早く続いていく期待である。そして、AI(人工知能)については、市場回復を大きく引っ張る期待のもと、各社の活発な取り組みが続けて見られている。
[→続きを読む]
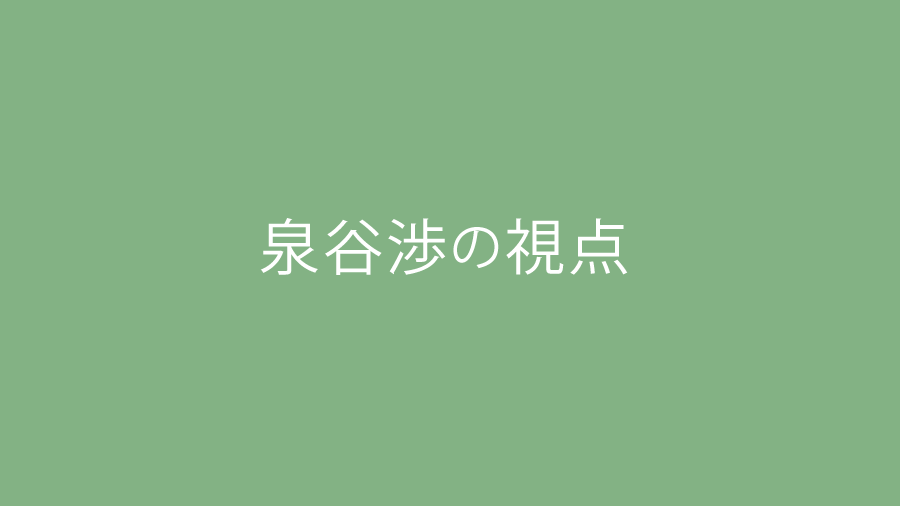
2024年1月 5日
|泉谷渉の視点
2024年を迎えて、希望に満ちたキーワードは何かと考えてみる。それはやはり、何といってもAIのもたらす未来社会の本格的開幕しかない!と思えてならないのである。
[→続きを読む]