MEMS���Ȥ�ȯŸ���ä�

�����١�������ظ���ʬ�Һ����ʳع������浡������ޥ����������ƥ�ͻ�縦�泫ȯ����Ĺ�Ǥ��빾��������Τ����դǡ�ʿ��26ǯ1��9����10����ξ���ˤ錄�äƳ��Ť��줿��Ĥθ����ʻ��ͻ���1��2�ˤ˽��ʤ��뵡���Ϳ���Ƥ����������� [��³�����ɤ�]
» �֥��� » ���������� » �����ĸ����ε��ѤĤ�Ť�

�����١�������ظ���ʬ�Һ����ʳع������浡������ޥ����������ƥ�ͻ�縦�泫ȯ����Ĺ�Ǥ��빾��������Τ����դǡ�ʿ��26ǯ1��9����10����ξ���ˤ錄�äƳ��Ť��줿��Ĥθ����ʻ��ͻ���1��2�ˤ˽��ʤ��뵡���Ϳ���Ƥ����������� [��³�����ɤ�]

���공ǰ�������Ѥ����æ�Ѥ�����Τ��ȤĤ��Ť�������������˴ؤ�뤳�ȤʤΤǤ��Υ�������Ū�ˤϱ��ʤ����⤷��ʤ����������١�50ǯ�ۤ��ε�ǰ���������줿�褦�ʵ��������Τǡ��Ѥ��ΤǴ����ƤޤȤ�Ƥߤ�����ȿ�̶��դȤ����ɤ�Ǥ���������й����Ǥ��롣 [��³�����ɤ�]

��ǯ��1��30����2��1��������ӥå������Ȥ�nano tech 2013�ʻ��ͻ���1�ˤ����Ť��줿��ǯ�����¤��졢�����ˤʤäƤ����Τ�ȩ�Ǵ�������Τϴ�Ф�������ǯ��ҡʻ��ͻ���2�ˤ�����������Ȥ䡢���浡���μ�Ĺ���뤤����ض������饹�ޤǤ��������Ȥ��ƥ֡�����Ω����������ǫ���äƤ����Τ⤳��Ÿ�������ħ�Ǥ��롣ɮ�ԤΤ褦���ȿ���������狼��ʤ����Ȥڤ�ʹ����Ķ��ä��ԤˤȤäơ���������������������Ȥ������ǰ��˲�ä������Ļפ��⤫�Фʤ��ä����ˤĤ��Ƥⵤ�դ�����뤳�Ȥ�����Τϡ����Ѥ��꤬�������ȤǤ⤢�ꡢ�ڤ������ȤǤ⤢�롣 [��³�����ɤ�]

����ʻ��ͻ���1�ˤǡ����Ѳ��Τ��������Ϥ�ȯ��������Ȥ��ơ���¿���ζ��Ӥ˿��줿����¿�����ƹ�Υƥ����������ĥ���ġ������ݥ쥤�ƥåɤǡ�1Tr. 1C�ʰʲ�1Tr���ȵ����ˤδ��ܥ����Ȥä�4K DRAM�������ǽ��Ƴ�ȯ�����ʻ��ͻ���2-4�ˡ�����θ��Ƥ�����������˻��´ط���ǧ�Τ��ᡢ���٤���¿���Ȼ修���路��������¿˻���桢���Τ��٤Ƥ��Ф��ƴ�¿��ᤫ�餴��ǫ���ֻ���ĺ���������λ修����ˤⳫȯ���ѼԤ˹������������������ɤ��Ȼפ������Ƥ�¿���ޤޤ�Ƥ�������¿���˸�ɽ�Τ��Ǥ����Ȥ����������줿�Τǡ������³�ԤȤ��ƾҲ𤷤Ƥ�������������Ǥ����������˸����修��ޤ�Ƥ��롣 [��³�����ɤ�]

��ǯ���ݥʥΥƥ��Υ���������Ÿnano tech 2012�ʻ��ͻ���1�ˤ����Ť��졢¿�������Ԥ�����ä�������Ÿ���������ϥѥͥ�ȡ����Ӥ����ä��Ǻ��Ÿ��������ä��������Ťͤ뤴�Ȥ˷������Τ�Ÿ�������褦�ˤʤäƤ��롣���������ή������Ȥ�¿������ˤ���ض�����ºݤ˸���˷Ȥ�äƤ�����ι�����Ԥ⤪�ꡢ��ǫ���������Ƥ���������Τ����Ѥ��줷������������ǯ���罸ͽ����Ÿ�������Ѥ��ĥ����褦�Ǥ��롣��������ǰ�ʤ��餽���Ǻ����Ѥ����µ���Ÿ���ϡ��ޤ����ʤ��Τ������Ǥ��롣�絬�ϻ��Ȳ��ؤ�ƻ�ڤ��ޤ������Ƥ��ʤ��� [��³�����ɤ�]

�����١�ɮ�Ԥ�CCD��������λ��Ȳ����������������ˡ�������Ҽ��������̳�ǥ����ݥ졼�ȥꥵ�����ե������Ǥ��������Ƿ��ζ��Ӥ˴ؤ��ơ�Ĵ������ɮ�������ô�ä�����湯���ԡ�����Ԥ�˭�������ϽФ������Υ١������סʻ��ͻ���1�˽��ǤΤ���Ǥ��롣������̤�¿���Τ��Ȥ�ؤ���Τǡ����ҤǤϸ��Ԥ��ʤ��ä���ʬ���ä˳�ȯ��Ǥ�ԡ����ѼԤο��������̤�������ޤȤ���� [��³�����ɤ�]

���ķ�¬��ü�κ��ĤǤϥ���ȥ�ץ�ʡ����åפ��٤���Τ���¤�����ܤ������Υ١����������Ȥ��ƽ��Ǥ�������̤��ơ��оݼԤζ��Ӥ��Τ餷�����Ȥ�ԤäƤ���ʻ��ͻ���1,2�ˡ������١�ɮ�Ԥϡ��ѥ�����ʤɤΥϡ��ɥǥ��������ɼ�إåɤȤ��ƻȤ��Ƥ���ȥ�ͥ뼧�����̡ʰʲ�TMR��ά���ˤ����Ū����ԤȤ��ơ�������ظ���ʬ�Ҳʳع������浡�������ε������������ζ��Ӥ�Ĵ������ɮ�������ô�ä�������ȯ������Ƥ���ʻ��ͻ���3�ˤΤǡ������ǤϤ���;�ä�ޤȤ����
[��³�����ɤ�]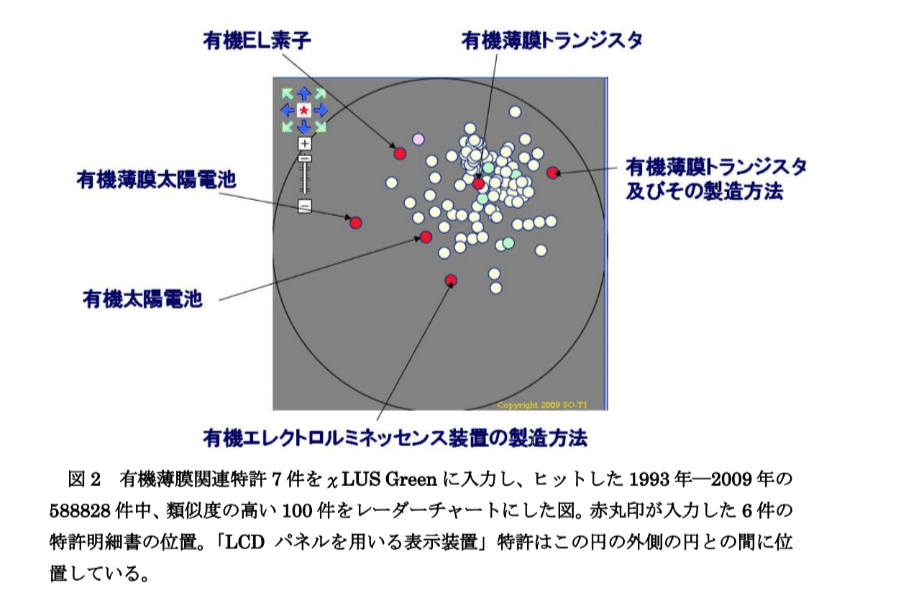
��ǯͭ�������Ϣ�θ��椬��ȯ�˹Ԥ��Ƥ��롣���ܸ��⡢����Ω�Ϥ��Ƥ���ȾƳ�λ��Ȥ�١����ˡ������˻����ؤˤ��ͭ�����쵻�Ѥ�ˤȤ��뵻�ѵ�������������������ϰ軺�Ȥ��ϽФ��褦�Ȥ��Ƥ������1�ˡ���Ƭ��Ω�äƻش����Ƥ���Τϡ�Ʊ�����ȵ��ѥ����������������2�ˤǤ��롣����2009ǯ2��˷��ܸ�ͭ�����츦������3�ˤ���Ω���졢10��ޤǤۤ����Ǯ���ˡ����Ĺ��٤����Ƥθ���Ť��줿�� [��³�����ɤ�]

���Ԥ���ǯ�ϸŴ���ޤ��롣�Ф�������ä��������ʤ롣���������ä�ȺФ�Ȥä��ȸ����롣���줬���Ǻ��ޤǤ��ޤ��������뤳�ȤϤ�����ʤ��ä��������ߥ���ݡ����������Խ�Ĺ��AEC/APC�ε�������1�ˤ��Ҹ������Ĥ��������˶��줿��AEC/APC�δ����õ���ɮ�Ԥˤ����뤫�˼��餷�Ƥ�������Ǥ��롣 [��³�����ɤ�]

����Ǥȥ��ץ饤�ɥޥƥꥢ�륺����ѥ������Фơ����ߤϷ��ܸ����ȵ��ѥ�����Ĺ��Ƥ��������������ꡢ����ιֱ��ǿǤ��褿�Τ�2008ǯ6��Ǥ��ä�������ζ���ɮ�ԤˤȤäƤ����곰�Υơ��ޤǡ������礷���֡������ΤϳΤ��ˡ���α�ޤ�ϥ饤����ɤ餮�ޤ����ǡ�ȾƳ�ΤϤ�ŷƻ�ͤޤ��������Ȥ�Ʊ�����Ȥ��������⤢�ä����������פȸ����ȡ���Ф��դ���֤����ǤϤʤ��������ϰ迶������������Ϣ�Ȥ����פȸ����Ƥ��롣���ΰ�ġפȤΤ��ȡ��ҤȤޤ�����Ū��Ȥ����ڤ���ʤ鿷�����⤢����������ޤȤޤ뤫�ݤ����ܸ������դ��ʤ�����Ĵ���Ϥ��Ƥߤ褦�Ȥ������Ȥˤʤä��� [��³�����ɤ�]
<<���Υڡ��� 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ���Υڡ��� »