半導体戦略議論についての提案
昨年末からの半導体の供給不足報道に続き、5月後半以降、政府や自民党における半導体戦略議論についてのニュースが多く伝えられた。「製造基盤の強化」が強調されている印象があるが、経済産業省の資料(図1)を見ると、エコシステム全体を面で捉えた競争力アップに取り組む姿勢も読み取れる。 半導体関係者の期待感は非常に大きい。 気になるのは、「政策投資を、どのようなプロジェクトで、どのように進めるのか」との点と思う。 そこで、20数年前、「ロジック半導体」が行き詰まった時に経験した問題(What to make)」を今一度振り返ってみたい。
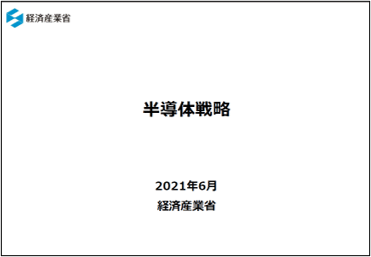
図1 経済産業省は、2021年6月4日、半導体・デジタルインフラ・デジタル産業の今後の政策の方向 性について検討するため、「半導体・デジタル産業戦略検討会議」を本年3月に設置し、「半導体・ デジタル産業戦略」を取りまとめ、Web上に「ニュースリリース」として公開した。
出典 : https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210604008/20210604008.html
少量多品種事業が縮小した時代
筆者が勤めていた半導体企業は、1990年代後半、DRAMの工場や人的リソースをロジック系事業に転換する作業を進めた。その中で良く言われたのが、「How to makeには強いが、What to makeに弱い」との社内の体質だった。
DRAMやSRAMなどのメモリは、商品の世代が更新しても仕様が大きく変わることがなく、また、そもそも商品の仕様は、北米や国内の標準化機関にてオープンに議論され決定して行くので、それらの議論に参加することを通じて「仕様」を完成させることができた。メモリは、商品企画策定の方法論が明確であった。
一方、年々、集積度を増やしチップの統合が進んだ「当時の先端ロジック」においては、商品の仕様設計は「難問」とされていた。今から思えば、「ロジック商品の仕様策定」が難しいのは、当時、「デジタル家電」と呼ばれたカスタムロジックの比率が多かったことが一因していたと思う。「カスタム品」は、特定顧客の独自な技術である「ユーザーロジック」に基づく少量多品種の集積回路商品であり、「標準」とは対極にある商品であった。
本来、半導体の製造技術は印刷技術であり、集積回路をマスクパターンに焼き付け、輪転機を回すように大量生産することを基本としている。 そこで、1970年代から80年代のロジック設計者は、多様な顧客のニーズと自社の印刷型大量生産技術を調停する手法(ゲートアレイ技術)を開発して来ていた。
ゲートアレイは、「配線次第で様々なゲートに変更しうる素子(バルクパターン)」を予めシリコン基板上に形成しておき、それらの素子を元に、製造の最終段階である配線工程で、「短手番で顧客が求める回路に仕上げる」という技術であった。「顧客が求める回路」から「配線マターン」を計算機処理で生成するソフトウエア・ツールの開発能力と、多くの顧客ニーズに対応可能なバルクパターンを設計する能力が競争力の源泉であった。ゲートアレイもまた、商品企画の方法論が明瞭な商品であった。
日系企業の「ロジック半導体」の敗退は、そのゲートアレイへの先行投資を停止することから始まったと筆者は思っている。 当時、社内のコスト管理の体系では、「事業のオペレーションコスト=製造コスト」であり、ゲートアレイ技術開発のような先行R&D費用は、総掛かり費用とされていた。従って、円高のために、コストダウン活動を強化せざるを得なくなった時、真っ先に取り組んだのは、チップ面積縮小であった。チップ面積が小さくなると、ウェーハからの収量が増え、チップ単価が下がるからである。
ゲートアレイは、少量多品種に対応すると言っても、多様な顧客のニーズに対応するようにバルクパターン設計するため、面積がどうしても大きくなりがちである。従って、顧客のコスト要求に対応できない事象が増えた時、ゲートアレイには、将来性は無いと社内の経営判断が下された。ゲートアレイの新規開発は疑問視され、社内のリソースは、SoC(System on Chip)事業に転換していった。
SoCは、ケイデンス社やシノプシス社等の社外のソフトウエアのライセンスを受けて、ロジックチップをバルクパターンから設計するという事業であった。 人手がかかるが、チップ面積は小さくなり、チップ当たりのオペレーションコストは小さくなる計算である。顧客にゲートアレイよりも安価な見積価格を提示できる。社内では、SoC事業で提示する見積り価格は、「グラム何円だ」などと揶揄されることがあったが、そのジレンマをなんとかしようという動きは始まらなかった。 顧客に提示する時に参照する「コスト」が、その製品の「オペレーションコスト」であり、「コストPlus」の方針で価格を見積もっていたからである。
結果、同社内におけるゲートアレイの時代は0.15umの世代にて終わったのだが、世界的には、ネットワーク向けカスタムロジック市場では、ゲートアレイよりも遥かに高価なFPGA(Field Programmable Gate Array)が使われるようになった。グラフィックス向けはGPUを始めとするASSPが優勢であり、民生向けの小規模な回路は安価なマイクロコントローラ(マイコン)であった。「FPGAを社内でも開発したい」と臨んだエンジニアはいたが、FPGAの特許の壁に挑戦する動きとはならなかった。
SoCで売り上げを伸ばすには、顧客からの設計要求を獲得する営業活動とチップ設計に要する人員が必要であった。ビジネスプランは明瞭ではあったが、エンジニアからは、商品企画や仕様設計への関心が薄れることとなり、ロジック事業は人海戦術で、シリコンをチップ面積に応じた価格で販売する事業へと変わって行った。社内で、「『How to make』には強いが、『What to make』には弱い」と言われたのは、その時期であったと記憶している。
What to make(何を作るべきか)
筆者は、ロジック半導体事業の弱体化は、1980年代に起こった「デジタル家電の興隆の時代」に種が撒かれ、1990年代に起こった、日系デジタル家電の衰退の段階で発火したと思っている。
アナログの時代の回路は小規模であったのに対し、デジタルは計算と論理を積み重ねることで巨大化させやすく、果てはインテリジェントとなる可能性を秘めていた。一般に、「ユーザーが望む計算を、より簡単に行えるロジック」が、良いロジックであった。言い換えるとデジタルは、「計算+論理の世界がどれ程に広いのか」にチャレンジする事業であった(参考資料2)。
但し、デジタルはチップ設計でも、またセット商品の設計・製造においても、参入障壁がアナログ時代に比べ低く、技術の拡散が非常に容易となっていた。技術の陳腐化リスクが大きな事業であった。そのため、デジタルのビジネスにおいては、独自技術クローズ化(知財権としての保護)と、オープンにすべき標準化の両面をマネジメントしなくてはいけない。また、技術の追随者に市場シェアを奪われることが無いように、顧客やアプリケーションの開発者に提供する技術を間断なくレベルアップして行かなければならない。ソフトウエアの開発者の支持を得ることが、ある意味では顧客の支持を得るよりも重要であった。
日本国内の多くのロジック事業が、なぜ「What to make」に弱かったのか
本来、従業員を雇用し、工場への設備投資を済ませた後に、「What to make」などという質問が発せられるというのは異常事態である。この異常事態は、アナログからデジタルへという破壊的イノベーションのインパクトを正しく理解していなかったために起こったのではないだろうか?
デジタルでは、計算と論理の進化の障壁となる様々な問題を一つ一つ取り除いて行くことが仕事となる。 回路開発のツールだけではなく、OSや開発ツールに関する様々なソフトウエア、顧客での実装や試験、トラブルシューティング等々。 一見、売り上げにはつながらない価値ある仕事が様々にある。1社では対応しきれないサポートサービスや要素技術が様々に存在する。デジタルのエコシステムは、競争的というよりも、協調的に棲み分け、互いに補完する世界である。
その協調的エコシステムの中で、企業の存在意義の再定義が必要だったのではないだろうか。デジタル家電の興隆というクッションと半導体協定という束縛の中で、思考停止したまま、「What to make」を考える能力を失い、1995年以降のIT(コンピューティング)と「Customer Satisfaction重視”の時代に突入してしまった。
IT時代の商品企画
筆者は、IT(コンピューティング)の時代を追体験しなくてはいけないと思い、この数年間、「コンピューティングとは何か」を調べて来た。以下は、その元での感想である。
1994年に日本版が刊行されたロジャー・ペンローズ(物理学者)の著作(「皇帝の新しい心」、参考資料3)によると、コンピューティングの原点は、「アルゴリズムを進める装置(回路)はどのような構成を取るのか」との1930年代の問題提起であったという。
集積回路のユーザーが実現したいと考える動作(アルゴリズム)と、そのアルゴリズムを実行するのに適した良い集積回路の構造は、技術が大いに異なる。技術のレイヤーが異なると言われることもある。前者は刻々と陳腐化しうる特定のアプリであるのに対し、後者は、市場ニーズの全体を見極め、ターゲット・ニーズを実装可能な回路構造を差別化技術としなくてはいけない。 差別化技術に必然性があれば、その存在意義となる。
工学技術としての回路の進化形が何であるかに関しては、特定のアプリケーションはほとんど何も教えてはくれない。デジタルテレビもビデオもデジカメも教えてくれはしなかった。 恐らくは、自動車も教えてはくれないだろうと思う。何も教わることはなかったのは、「ユーザーロジックを実装サービスする技術者は、ユーザーロジックを勉強してはいけない」という商慣習の面からは当然ではあった。そして、日系企業は、アプリケーションを実装するための「集積回路の基本アーキテクチャ」に関しては市場ポジションも競争心も失ってしまった。
また、経営者も、半導体集積回路が、コンピューティングの時代に突入した時に、アプリケーション志向から脱し、自らの存在意義を賭して、市場が不可欠とする投資を真っ先に行い、エコシステムの中でポジションを確立するための計画を実行しなくてはいけなかったのだ。 正しい開発投資であれば、商品として成功しなくとも、事業としての買い手が付く。
北米では、そのようにして事業に取り組むリーダーと投資家が存在し、両者が互いに協力することで、MPU、FPGA、GPU、ネットワークプロセッサ等の技術を担う企業を育てることができたと思う。 もちろん、彼らが育つには、強力なアカデミズム、IEEEのようなNPO、各種のフォーラムやコンソーシアムを運営する人材やノウハウや助成金も寄与したのだと思う。 また、それらの活動を促進する様々な事業環境のセッティングにおいては、政府による環境整備もあったのだろう。
ではどうするのか
今、そのようにして進んだ先端ロジックの大競争も、実は、既に、終盤戦にあると筆者は思う。市場では既に寡占化が進み、多くの分野で参入障壁は目が眩む程に高い。したがって、半導体戦略議論にては、次の風を捉えた戦略となるべきだろうと思う。但し、その風は、アプリケーションが吹かす風ではないはずだ。
筆者は、次の風は、「確率プロセス(マルコフ過程)を演算する回路へのニーズ」だと思っている。そして、その風が変革するのは、サーバだろうと予想する。確率プロセスは、集合を扱い、確率演算を多用し、新たな知見を出力する。そのような演算に適した集積回路の新開発競争は既に白熱しているが、未だ、その市場ニーズを見極め、それに向けて工学的な必然形を探る余地があると思う。 エコシステムを巻き込んだ大きなプロジェクトが必要であると思う。
その新進化においては、コンピュータサイエンス、コンピュータグラフィックス、ネットワーク理論が、1990年代以降の先端ロジック商品の回路開発を支えたように、サイエンスが市場ニーズや回路開発と共振する必要があるとも思う。日本の半導体設計者は、総じてサイエンスとの関わりが薄いが、これは大問題である。
リスクが高い故、その新進化のビジネス立ち上げにおいては、一企業の枠を超えた、面のレベルでの取り組みが必要なはずだとも思う。 政府による様々な支援は必須である。 R&Dの強化、NPO活動の強化、企業活動が内向きから外向きに変貌しうるよう事業環境整備、企業の若返り、そして、「What to make」の明確化の推進、等々が行われて欲しいと思う。
参考資料
1. 半導体・デジタル産業戦略
2. 丸山不二夫(MaruLabo)の講演ビデオ、「人工知能技術の10年」、「計算可能性理論と計算複雑性理論」、「量子コンピュータと計算科学」、等々。
3. ロジャー・ペンローズ、「皇帝の新しい心」、p.40、みすず書房刊、1994年


