宇宙利用とAIチップが結びつく、EdgeCortix SAKURA-Iが耐放射線強さを実証
エッジでAIを利用しようというAIチップを開発している国内のスタートアップEdgeCortix社(参考資料1)の「SAKURA-I」が実は、宇宙環境でも使えることがわかった。先週東京ビッグサイトで開催された2024国際航空宇宙展で同社が明らかにした。米航空宇宙局(NASA)の重イオンやプトロンを放射された環境で故障しなかったのだ。
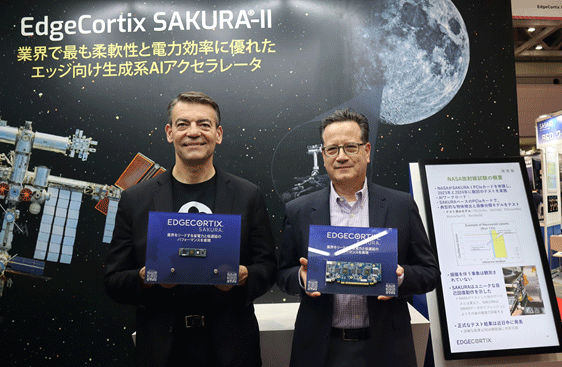
図1 放射線に強いことが証明されたEdgeCortixのAIチップ 右がマーケティングおよびUSオペレーション担当EVPのJeffrey Grosman氏、左は防衛&宇宙技術担当VPのStan Crow氏
エッジAIの応用の一つが宇宙船内でのAIチップ利用だ。これまで宇宙用ICというと高信頼性が求められる特殊な半導体というイメージだったが、実は宇宙が徐々に身近になってきている。宇宙ロケットは国防から民間利用へと広がってきている。しかも、SpaceXのような民間の打ち上げロケット企業や衛星開発企業なども出てきた。さらに通信衛星として5Gから6Gへと移る前に徐々に、宇宙での基地局など2次元的な広がりから3次元的な広がりへと進みつつある。セルラーではないが、Bluetoothで地上と宇宙空間の通信を成功させたという例もある(参考資料2)。
とはいえ、宇宙では多数の放射線が飛び交っている。半導体の空乏層は、電子・正孔対を作るのにピッタリの電離層でもある。特にDRAMやSRAMのようなメモリはビット反転を起こしやすい。1が0になり、その逆もよくある。半導体は宇宙線に弱く、宇宙での利用ではECCなど誤り訂正回路は必須だった。
一方NASAは、宇宙で使えるAIチップを探していた。衛星やロケットの民間利用が進むにつれ、半導体チップにもAI機能が求められるようになって来たからだ。そこでAIチップとして宇宙船や衛星などで使える半導体としてGPUやGPGA、CPUなどがあるが、どれも結局、そのまま宇宙での利用には適さないものが多い。宇宙ではスペースが、限られているため小型、低消費電力、そしてもちろんAI処理能力の高さなどを全て満たす必要がある。これは自律走行システムで使うためだ、と防衛&宇宙技術担当VPのStan Crow氏は語る。
宇宙で、しかも自動走行車に使うとすれば小型、高性能(リアルタイム動作)、低消費電力、耐放射線に強いという条件が欠かせない。NASAは、EdgeCortixのチップ「SAKURA-I」に目を付け、NASAのNEPP(NASA Electronics Parts and Packaging)計画の下で今年の1月に放射線テストを2カ所で行った。最初はマサチューセッツジェネラル病院で、重イオンやプロトン(H+)などを照射した。特に最近の放射線治療では、癌細胞だけをたたくため、質量の重い重イオンを使うことが多くなってきた。これまでのように放射線元素の質量が軽ければ癌細胞を付き抜けて正常細胞まで傷つける恐れがあるからだ。
次に、放射線の科学で定評のあるLawrence Berkeley国立研究所で行った。いずれの場合も複数のテストを行った結果、一つも破壊しなかった、とCrow氏は言う。しかも経時変化でも特性は変わらなかった。
SAKURA-Iにはもともと自己回復機能があるというのだ。セルフリフレッシュのような機能で放射線によってデータが反転してもすぐに回復するという。メモリで使われているような誤り訂正回路ECC(Error Checking and Correcting)は使っていない。ただ、ソフトウエアでモニターしておき、もし誤ったら信号経路を戻り正常モードで再現してみるという。同社はなぜそうなるのかについて説明してくれなかったが、実質的に学習して修正しているのかもしれない。このAIチップは本質的に放射線に強いのだという。「将来はECCを使うかもしれないが、今のところは必要ない」と述べている。
このため、SAKURA-IIに対しても放射線テストを行う予定だが、SAKURA-Iよりもっと良いデータになりそうだ、と自信を見せている。TSMCの12nmのFinFETプロセスで製造しており、SAKURA-Iよりもチップは小さいが、「アーキテクチャに自信があるので放射線には強いと思う」とCrow氏は述べている。
参考資料
1. 「日本生まれのファブレスEdgeCortix、本格的な生成AIチップを製品化」、セミコンポータル、(2024/05/29)
2. 「Bluetoothで衛星と通信した、スタートアップのHubble Network」、セミコンポータル、(2024/05/09)




