世界最大最高レベルの先端半導体研究所に成長した秘訣と今後の戦略
ベルギーimecのVan den hove CEOインタビュー:
今から40年前の1984年、半導体産業とは無縁のベルギーの片田舎、ベルギー・フランダース地方(ベルギー北部のオランダ語圏、日本では「フランダースの犬」のアニメで有名)に大学の共同利用クリーンルーム・研究施設であるInteruniversity Micro Electronics Center(imec)が誕生した。40年後の現在、imecは、世界最大かつ最高レベルの最先端半導体研究所に成長した。同社のLuc Van den hove CEOが、東京で年次研究紹介イベントimec Technology Forumを開催のために来日した機会をとらえて、本稿著者らメディアのインタビューに応じた(図1)。同社の目覚ましい成長の秘訣と今後の戦略を読者諸氏と共有することにしよう。

図1 インタビューに応じるimec CEOのLuc Van den hove氏 2024年11月5日東京都内で著者撮影
創立以来10年ごとにビジネスモデル革新
Q: imecは、今年、創立40周年を迎えましたね。この間、目覚ましい成長を遂げましたが、成長の秘訣は?
A(Van den hove CEO): 当社は、今から40年前の1984年にベルギーで非営利組織としてわずか70人で発足した。いまは5500人にまで増加している。この中には、正規社員のほか、世界中の会員企業(研究パートナー)から派遣されている駐在研究員が700人、さらにベルギーだけではなく世界中の博士課程学生とポスドク(博士号取得直後の)研究員があわせて850人を含んでいる。
創立当時、今日のような世界最大級の先端半導体研究施設になることは想像できなかった。
創立から10年後の1994年にIndustrial Affiliation Program (産業界各社との協業プログラム)を開始し、さらに10年後の2004年に300mm Core CMOS Program(半導体企業と先端CMOSを共同開発するプログラム)を始めた。2014年には、ベルギー・フランダース地方政府のデジタル技術研究センター(各大学に分散研を設置)である iMindsを吸収合併し、半導体応用研究に注力するようになった。そして、2024年には、世界の半導体業界が転換点を迎え、欧州、米国、日本の各政府が地政学上の理由でCHIPS法(各国の半導体製造を強化するするために補助金支給の法律)を施行したのに伴い、当社としてもこれらの政府と協調することにした(図2)。日本でも半導体産業振興に協力するため、経済産業省とラピダスやLSTC支援についてすでに合意した。このように、当社は創業以来、10年おきにビジネスモデルの革新を図り成長を遂げてきた。
Q: 以前は中国の企業や大学とも多数の研究提携を行っていたと思いますが、現状は?
A: 確かに数年前までは、なんの問題もなくそうしていた。しかし、今は、地政学上の理由で中国勢とは距離を置いている。中国の大学との研究提携もやめている。
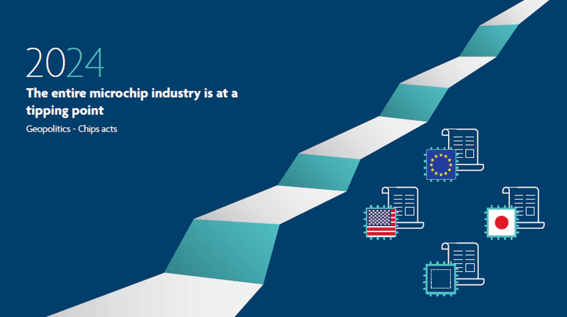
図2 imecの2024年のビジネスモデル革新 出典:imec
imecの研究パートナーの日本企業は66社
Q: imecの会員企業(研究パートナー)はどのくらいの数ですか?
A: 現在、IDM/ファウンドリの会員企業は、Intel, Samsung, TSMCはじめ24社で、日本のソニー、キオクシア/Western Digital、ルネサスエレクトロニクス、ラピダスもメンバーである。装置メーカーは、ASML、Applied Materials、東京エレクトロン、SCREENはじめ40社余り、材料メーカーはEntegris, JSR, 東京応化はじめ30社、ファブレス・EDAベンダーは40社、システムパートナーは100社余。日本企業は、全部で66社が加入している(2024年10月現在)。今年、正式にimec日本法人を東京に設立したので、さらに多くの日本企業パートナーを勧誘していくつもりである。
Q: imecの予算規模は?
A: 予算規模は創業以来毎年増えており、2023年時点で9億4000万ユーロである。初期にはフランダース政府から1割程度の援助を受けていたが、現在は、オランダの研究支所にオランダ政府の支援があり、EUの研究プロジェクトにも積極的に参加しているので、これらの政府からの収入は全体の2割に増えている。残りは、世界中の多数の研究パートナー企業からの研究委託費収入である。
新たに北海道大学と2nmロジックのユースケース開発
Q: 日本の大学や研究機関とも研究連携していますか?
A: 東北大学、筑波大学、横浜国立大学、名古屋大学、大阪大学、九州大学はじめいくつもの大学と研究連携している。今回(2024年11月)、北海道大学とも研究提携して、2nmロジック 半導体のユースケース開発に重点を置きつつ、半導体分野の進展に向けて、地域の研究開発企業とも連携し、日本の半導体エコシステムの発展に貢献するための連携の機会を模索することにした。日本政府系の理化学研究所、物質・材料研究機構やLSTCとも研究提携している。
東京と北海道に研究拠点設置する協議中
Q: 日本に研究施設を設置する計画があると1年前に伺いましたが、進捗は?
A: 多数のパートナー企業が集まっている東京と、ラピダスや北海道大のある北海道に研究拠点を設けて大学や研究機関との連携を進めることにしている。現在、経産省と協議中であり、最終決定に至ってはいない。クリーンルームを持った大規模な研究所ではなく、ベルギーの研究施設のサテライトオフィスといった感じの施設を考えている。イノベーションを生み出すためには大学だけではなく幅広いパートナー企業との連携も必要である。
車載チップレットプログラムに日本企業の加入勧誘
Q: imecは、最近、車載チップレットプログラムを発足させ(参考資料1)、BMWやARMはじめ10社が加入していますが、ルネサスやトヨタなど日本企業の加入はあるのですか。
A: 日本企業の参加は大歓迎だ。数社と交渉中だが、今はこれ以上何も話せない。

図3 imec車載チップレットプログラムの初期参加企業10社 出典:imec
先端デバイスの歩留まり向上は半導体メーカーの仕事
Q: imecのパートナーである米Intelや韓Samsung Electronicsは、3/2nmプロセスでの歩留まりが低迷しています。imecは歩留まりを上げるための支援するつもりですか。
A: imecの役割は、業界より5−10年先の最先端プロセスモジュールを開発して会員企業に提供することである。製造ラインの歩留まり向上は、各半導体メーカー自身がやるべき仕事で
ある。
High-NA EUVがムーアの法則を延命
Q: High-NA EUVリソグラフィの意義とimecクリーンルームへの導入予定は?
A: High-NA EUV リソグラフィ装置(従来装置の開口数NA=0.33に対してHigh-NA装置はNA=0.55)の登場で、ムーアの法則は、少なくとも2030年半ばまで延命できる(参考資料2)。さらに、その後、NA=0.75のHyper-NA EUVリソグラフィ技術が開発され、さらには、トランジスタのチャンネル部分をシリコンから2D(2次元)材料で置き換えた2DFETが開発されれば、ムーアの法則はさらに2040年代に向けて延命できる(図4)。
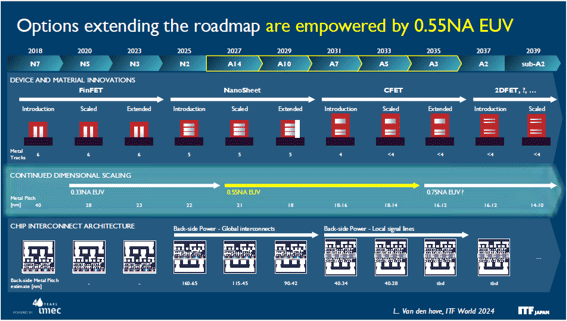
図4 High-NAの登場でパワーアップしたimecの先端ロジックロードマップ 出典:imec
imecのHigh-NA EUVリソグラフィ装置導入の第1段階を蘭ASMLとの共同研究所High-NA EUV Lab(蘭ASMLの本社キャンパス内)でのパターニングプロセス開発とするならば、第2段階は、2025年にベルギー・ルーベンにあるimec本社キャンパスにある既存の300mmクリーンルームである「Fab3」への設置である。さらには、2026年までに、Fab3 にすでに設置して活用している従来のN=0.33機と、性能、スループット、プロセスコストなど様々な比較を行う。これが第3段階。そして第4段階は、EU CHIPS法により本社キャンパス内に新設する「Fab4」(2025年着工、2027年稼働開始)にHigh-NA EUV装置量産モデルEXE:5x00を搬入して2nm超ロジックデバイス試作に活用する。
参考資料
1. 服部毅、「imecが車載チップレット研究プログラムを推進」、マイナビニュースTECH+、(2024/10/16)
2. 服部毅、「imecが高NA EUV活用でムーアの法則の延命を宣言」、マイナビニュースTECH+、(2024/11/13)




