地味なパワーデバイスに脚光が集まる反面、気になる台湾TSMCの動き
これまで地味な分野であったパワー半導体に注目が集まっている。パワー半導体の設計・製造法も従来のシリコンプロセスとよく似ており、大電力を扱うための均一化、バラスト、少数キャリヤをうまく利用する方法などの問題はシリコンプロセスと一緒だ。しかし、放熱の問題、熱抵抗をいかに下げるか、という独自の問題もある。大電流だとわずかなインダクタも考慮するRF技術との類似性もあり、半導体の総合技術といえないこともない。
先週は、ルネサステクノロジが逆導通サイリスタを製品として市場へ出した。これは、自動車などの小型発電機(3相交流モーター)からの電圧をバッテリーに充電するためにACをDCに変換し安定なDCを電池に供給するためのパワー半導体。定格電流5Aで耐圧は400Vあり、TO-220という実績のあるパッケージに封止されたディスクリートデバイスである。逆導通サイリスタは逆方向にダイオードをパッケージ内に並列接続したもので、外付けのダイオードが要らないというメリットがある。
三菱電機はSiCのパワーデバイスを量産するために福岡市のパワーデバイス製作所のラインに35億円を投資、専用ラインを構築し、2011年第1四半期から量産を始めると日本経済新聞は報じた。4インチのSiCウェーハを月産3000枚流せるラインのようだ。2012年までに総額135億円を投じるとしている。SiCのパワーデバイスはMOSFETとショットキーバリヤダイオードが実用に近い段階に来ており、新聞報道には書かれていないが、デバイスの完成度から言って、おそらく最初に実績のあるショットキーダイオード、次にMOSFETを流すのではないかと思われる。残念ながらIGBTはSiCに向かないことは以前にも述べたので、IGBTがSiC量産品の選択肢に入ることはあり得ない。
パワー半導体の主な応用として自動車や二輪車の他、数A以上の電流を流す応用なら何にでも使う。スマートグリッドに欠かせない2次電池、再生可能エネルギー源となる太陽光・風力、潮力などの発電装置にも使える。いわば環境の切り札的な存在になりつつある。経済産業省が主催して国内の自動車、電機、電力などの企業が集まり、スマートグリッドの標準化を呼びかけたと日経新聞は報じている。標準化すべき分野や技術を順次IECにも提案していくとあるが、その前にこれまでの国内規格がなぜ国際標準になりえなかったかをしっかり分析し、その轍を踏まないようにしていくことが肝要だろう。海外企業はいきなり標準化会議に提案を出さない。個別の企業と根回しをしながら会議に提案してくる。国内企業は標準化の会議の前に海外のコンペティタも含め海外企業と議論していく必要がある。そのために海外企業に対して胸襟を開いて製品やシステム仕様についてディスカッションする。標準化に向け、国際化はマストだろう。経産省は国内企業へ呼びかける作業は終わったため、あとは国内企業が国際標準化に向けて海外企業と個別に話し合うことになる。
先週のニュースで気にかかったのはTSMCがらみのニュースである。台湾のファウンドリTSMCは1月12日に、富士通マイクロエレクトロニクスと28nm技術で共同開発し、11日に米国のファブレス企業ナンバーワンのクアルコムとも28nm技術開発で提携すると発表している。TSMCは、最近のアグレッシブな投資、数1000名といわれる規模のワーカーの採用など、将来の地位を獲得するための動きが活発である。
半導体各社みんながファブライトを指向するなら、TSMCは「半導体製造のマイクロソフト」になるだろう。どの企業も全てTSMCに製造を握られ、日本メーカーは供給・納期・価格・その他の価格などで何も言えない立場に陥る可能性は極めて高い。ここでその他の価格と書いたのは、ライセンスあるいはロイヤルティ的な料金を要求してくる可能性があるという意味をもつ。製造が得意なはずの日本国内にファウンドリがなく、いまだに内輪の競争に目がいくようではTSMCの思うつぼになる。NECエレでもない、ルネサスでもない、東芝でもない、完全独立のファウンドリがあれば、「TSMC詣で」の必要もなくなり、納期・価格・供給などの面でTSMCと競争できる立場になれるだろう。問題の資金はアブダビでも、どこでもよい。人はNECエレやルネサスをファブとファブレスに分離させて連れてきてもよい。日本の製造技術を生かし、世界企業と勝負し勝てるファウンドリの立ち上げは検討に値するはずだ。こういったアグレッシブな構想でも持たない限り、日本の半導体がかつてのワンツー独占を復活させることは難しい。
もう一つの問題は、富士通という製造プロセスにも精通している企業が製造を専門にしている企業と共同で28nm技術を開発するということは、富士通の考えている28nm技術がTSMCに渡るという意味である。クアルコムだとファブレスだからその心配は全くない。しかし、特に日本のIDM(垂直統合半導体メーカー)は自社の技術を相手に公開して納得のいかない工程を自社流に直すことをする訳だから、TSMCにまるまる手の内を見せることになる。技術の流出そして覇権を握られるという、この流れを断ち切るためにも国内ファウンドリは必要不可欠ではないだろうか。
できればIDMからファブレスとファウンドリを分離させることが望ましい。ファウンドリ企業としてプロセスエンジニアとして退路を断ち切らなければ、ビジネスは成功しない、さらにベンチャー企業がファウンドリを担うには危険が大きいからである。NECエレやルネサスにプロセスラインを残したままのファウンドリ構想は必ず失敗する。もちろん、ファウンドリには設計との、特に物理設計とのインターフェースを受け持つ部門は必要で、できれば設計上流のESL部門との連携もタイミング、消費電力の点で必要となる。このため設計エンジニアもファウンドリには必要なことは言うまでもない。
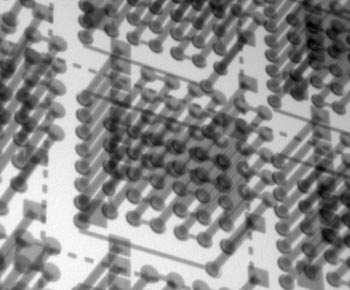
大日本印刷のTSVインターポーザー基板
LSI産業での新しいビジネスモデルが日本から生まれてきた。大日本印刷は3次元積層技術に必要なシリコンのインターポーザー基板を販売するというビジネスを始めた。さまざまなチップを縦に重ねる3次元ICでは、貫通坑で手っ取り早く上下のチップをつなぎ合わせたい。しかし、電極パッドの位置がメモリーとロジックでは大きく違い、そのままでは使えない。このため二つのチップの間にインターポーザーと呼ばれるシリコン基板をつなぎ合わせ、その上にロジック、その下にメモリーなど、異なるチップをTSVでつなごうという訳だ。これまで特注品だったインターポーザーに汎用性を持たせたという。




