製品の値上げで付加価値を売る、エイブリックの営業戦略
2023年6月にエイブリックの代表取締役社長執行役員に就任した田中誠司氏。2024年6月末には、経営のプロであり、エイブリックの会長兼ミネベアミツミの専務執行役員であった石合信正氏が退任され、田中社長はミネベアミツミの事業執行役を引き続き担っている。社長就任から1年経ち、エイブリックはどう変わったか。
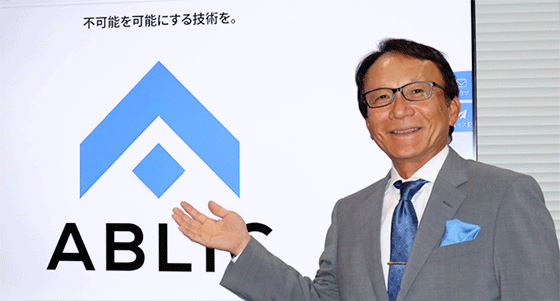
田中 誠司氏、エイブリック株式会社 代表取締役社長執行役員
石合氏は外資系企業の経営という業務のプロを歩んでいたが、田中氏もやはり外資系企業に長く、Motorola、そしてそこからスピンオフしたFreescale Semiconductorで合計25年経験、2012年にエイブリックに入社した。ずっと営業畑を歩んできた。
社長就任の1年間でどのような分野に力を入れてきたのか。
「私が社長になった23年の7月ごろ、ビジネス的に半導体産業はあまり良くなかった。半導体不足の逼迫状況の反動で、在庫調整ばかりの時期だった。そこで、マネージャークラスの人たちと製造・開発をメインに懸念や課題をいろいろ吸い上げてみたところ、新製品とか、付加価値の高い製品をもっと出さなければならないことになった。ミネベアミツミ本体からも、目標額、それも結構大きな金額を実現するためにやっぱり武器がもっと必要だと言われた」と述べている。
エイブリックはもともと時計の精工舎の流れをルーツに持つ会社だ。産業用というよりも民生用の製品が多く、どうしても過当競争に陥るような製品も多い。特に新製品の企画が足りないと感じたという。外資系の半導体メーカーには、マーケティング部門でしっかりと商品を企画する部隊がいる。「ここがエイブリックには欠けていた。これを作らなきゃいけないと入社以来思っていたが、なかなか実現できなかった。しかしようやくマーケティング部門を作ることができた。実際発足したのは24年の5月からだが、人選や組織の形態など、ちょっと時間かかってしまった」と田中氏は語る。
その5月から3カ月経過した。この間、具体的な活動に入った。目標値を達成するため、新製品を出してどこまで稼げるかを考えた。目標値とのギャップがどのくらいあるのかを正確に把握する作業を行い、その次に何をすべきかを今、マーケティング部隊が中心になって戦略立案しているという。
昨年まで、エイブリックとして7年間基礎を固めてきた。今はロケットに例えれば、その基礎の次の第2エンジン発進ということになる。エイブリックは2016年から発進して、振り返ると、今まで出来ていなかった日本のビジネスカルチャーが残っていたという。石合前会長の外資系的な考え方として、コスト削減、効率化など営業の施策は、田中氏もずっと外資系企業でやってきため、石合氏の営業施策とすごく合っていた。「私も2012年に入社して以来、いろいろと改革しようと思っていたが、1人ではできない部分が多かった。ここに石合氏が入社し、かなりサポートしてもらい一緒にやってきて基礎固めはできたかな」と感じている。
製品値上げの考え方
利益をきちんと生み出すために、エイブリックは製品を値上げした(参考資料1)。2017年、18年のころに田中氏自身も、ある顧客と10回以上対面して、交渉もしてきた。値上げするためにはまず、不採算の案件を全部洗い出した。それもお客ごとに洗い出してプライオリティを付け、どの顧客との製品を値上げしていくか、優先順位をつけてその担当の営業に交渉に行くように指示した。「営業担当者はぶつぶつ言うものの、不採算案件だから、もうビジネスがなくなってもいいと正直思った。だから、ビジネスがなくなってもよいから、値上げ交渉をしてくれと徹底した」と田中氏は述懐する。
エイブリックの得意なアナログ製品は顧客が簡単に他社に乗り換えることはできない製品だという。単価が数十円と安いため、顧客が他社に乗り換えようとすると、顧客の時間もコストもそれなりにかかる。仮に単価が50円として10%上げても、たかだか5円にしかならない。「それなら当社の値上げを飲んだ方が得策だと考えるようになる。このような客が多かった」と語る。
値上げというと営業マンは尻込みする。しかし実際やってみると、営業マンも自信を持つようになったという。「我々は製品だけを売っているのではなくて、付加価値を売っている、と当時よく言っていた」(田中氏)。エイブリックだと短納期や高品質という付加価値があるから、単価が高くても納期は守る、不良問題は起こさない。「このような付加価値を顧客に理解してもらいサービス価値に見合う価格で売ってもらうという指示を徹底した。エイブリックの付加価値を認めた顧客が多かった」という。
「営業マンは当初、値上げを言い出すことをビビっていましたが、そういうお客さんが認めてくださるというか、値上げを飲んでくれるのは、自分たちの製品の付加価値を、顧客がきちんとわかってくれるんだなということが自信にも繋がった。それはすごく我々の営業部隊のモチベーションになった。それからその業績は非常に大きく上がった」と田中氏は振り返る。
エイブリック社内でも営業の地位が上がった。今までは工場や技術者の方が偉い、といった風潮があった。石合氏は営業が一番強くないと会社は強くならないという考えを強く持っていた。実際に値上げしたことによって利益が改善してきた。2020年から22年に賭けて半導体不足の時は値上げ活動を積極的に行った。
海外の半導体メーカーは需給状況に応じて値上げを行っていたが、日本はこのような文化ではない。ユーザーは定期的にコストが下がるものと思っている節があり、コストダウンは当たり前という風潮があった。しかし、コストダウンは2017年から止めた、としている。
デジタルICはムーアの法則で微細化が飽和してきており、コスト的にはもはや下がらなくなってきている。昔のDRAMのように1世代ごとに微細化できていた時代ではない。ましてやアナログは微細化で集積度が上がり性能も上がるというわけではない。付加価値をきちんと説明し値上げを納得してもらうことが重要になる。そのためには、技術営業は顧客のエンジニアにアプローチして商品の付加価値を説明すべきであろう。「かつて営業が代理店と一緒に購買に行ったことがあったが、役割分担をすべきだろう」という。外資のビジネス文化を採り入れたことが功を奏したといえそうだ。
新製品の付加価値に工夫
バッテリ不要で、漏水を検出するIoTデバイスである「CleanBoost」の現状はどうか。大口、中口を含めて引き合いは強まっているという。2021年8月にNTTの無人基地局で採用され、運用開始している。これは基地局で水漏れがないかどうかを、定期的に点検しなくても済むというメリットがある。バッテリを使わないエネルギーハーベスティングな製品のため、保守費用はずっと安くなる。
NTT以外の顧客も少しずつ増えてきている。これまではセンサと無線タグを購入してシステムインテグレータがソフトウエアと組み合わせてゲートウエアなどで使うビジネスをしていたが、エンドユーザーの顔が見えない。そこでソフトウエアやゲートウェイをエイブリックがパッケージ商品として提供し始めた。また、漏水のセンサだけではなく、センサをもっとバリエーションを広げるように開発で進めている。
そのほか、車載用のパワーマネジメントICにも力を入れ始めている。40V耐圧で電流は1A程度のDC-DCコンバータなども用意しており、車載規格を満足している。医療機器では超音波診断装置用のICだけではなく超音波を使った魚群探知機や、非破壊検査装置などに向けたICも製品ラインアップが充実してきたとしている。
ミネベアミツミの半導体部門は、旧ミツミとエイブリックに加え、日立パワーデバイスも2024年5月に買収したことで大電力デバイスのIGBT(Integrated Gate Bipolar Transistor)もそろった。センサからアナログ、アナログとパワーのアクチュエータなど、手足となる半導体はますます充実することになる。24年度は1200億円程度の売り上げ見通しだが、28年度には2000億円の売り上げ目標を立てている。
参考資料
1. 「エイブリック、『やらされ仕事』から社員のキャリア形成へ転換、業績アップへ」、セミコンポータル、(2023/06/16)




