人工知能への道(5): 技術の収斂現象としての人工知能開発技術に向けて
ロジック系集積回路の歴史は、技術と産業構造の収斂の歴史でもある。 その収斂は、市場の力を通じて産業界を垂直統合型から水平分業に変化させ、設計事業やソフトウエア事業、製造事業を独立させ、ネットワーク型ビジネスを築いて来た。 その変化に際する企業とアカデミズムの地道な努力(技術仕様の整備、認証作業の立ち上げ、ビジネスモデルの確立)や政府の政策対応の影響や効果は非常に大きかったことを、ここでは振り返る。 日系企業と日本政府の政策は、正にそれら地道な部分で「弱点」を持つと思えるからである。
収斂(コンバージェンス)に関する様々な論議
2000年前後に使われた時の「ロジック技術の収斂(コンバージェンス)」は、「各種通信インフラのインターネットへの接続」や「技術のデファクト標準化」の意味だった。 その収斂は、技術が進化する時に生ずる「変化」の一つであったはずだったが、機会を捉えた「政府の規制緩和」や「金融緩和」が企業の投資を促したため、その変化は数十年に1度の大チャンスとなった。 その機会を捉えて大投資を決行した企業は、その後専業企業と見られるようになり、開発効率や量産投資の効率の面で垂直統合型企業を圧倒する存在に変貌した。 結果、日系企業は衰退し、ロジック系集積回路業界は、IT産業と一体化した水平分業体制に移行した。
「技術の収斂」との表現は、近年も使われる頻度がまた増えてきている。 AI(Artificial Intelligence)技術や、ICT(情報通信技術)産業に対する政策、自動車の分野が目立つ。 具体的には、「コンピューティングのクラウド化」、「AIの開発環境の収斂」、そして、それらの「収斂」によって生ずる「問題(プライバシー問題、監視経済化、シングルトンの発生(後述)」についてであり、例えば以下のような議論である。
2015年に、グプタ氏(インド、バンガロールのビジネススクールの教授)らは、情報通信技術産業における「収斂」が、インドの産業界にもたらしうる問題とチャンスを独禁法の観点から説明した(参考資料1)。
2019年に、エバート氏(ドイツ、シュトゥットガルト大学のコンピュータ科学の教授)と同僚は、現在は、自動車メーカー毎に分かれている車載用システム向けソフトウエアの「収斂」を予想した(参考資料2)。
2019年に、パーク氏(米国の科学技術政策の分析官)は、米国議会向けの報告で、電話、コンピュータ、カメラ、音楽再生機などの機能が単一のモバイルハードウエア(スマートフォン)に統合したことに対応して、規制管轄当局の側の体制が変わる必要があること。また、消費者や行政/法人の権利の観点から、デジタルプライバシーやデータセキュリティ、データ流通に関する規制や保護を検討する必要があると主張した(参考資料3)。
尚、2015年には、ヤンポルスキー氏(米国ルイビル大学のコンピュータ科学の准教授)は、自己改良能力を持つ「汎用的な能力を持つ人工知能」のソフトウエア・アーキテクチャは、一つの技術に「収斂」する可能性があるとした(参考資料4)。
それより前、2006年に、ボストロム氏(スウェーデンの哲学者)は、汎用的な能力を持つ人工知能が開発されると、様々な機械を人工知能が改良し、また、人工知能用のハードウエア自体も人工知能によって改良されるという事態が生ずるため、機械文明は指数関数的な速度で高度化し、単一の機械文明(シングルトン)に「収斂」すると大胆な仮説を提唱していた(参考資料5)。
そこで、これらの議論を参考として、「技術の収斂を引き起こした要因」をまとめてみる。
収斂を引き起こす市場からの圧力: 投資効率と利便性の最大化
2000年前後に用いられた時の「技術の収斂」は、「ディジタル技術が進展すると、通信と計算機の技術仕様は単一のアーキテクチャに収斂する」との仮説であった。
初期投資が大きく生産規模がコストダウン効果を持つ事業にては、開発や供給を1社に集中した方向が投資効率は高くなる。 従って、同業間の企業合併による「自然独占」が生じやすい(参考資料6)。 市場ポジションは、成功した投資や資金調達の金額の順となるからである。最上位の1社の投資金額は、次の時代の「参入障壁」となる。 集積回路設計や半導体製造は、正にそのような性格を持つ事業であった。
集積回路設計も半導体製造も、そのように共に投資能力や資金調達能力の高い1社に「収斂」する傾向を持っていたため、IDM(Integrated Device Manufacturer)と呼ばれた垂直統合型事業は難しい事業であった。 実際、多くのIDMは、Fabless化か、Foundry化の選択を迫られ、半導体業界は、「垂直統合型企業群からなる姿」から「水平分業体制」に生態系(エコシステム)を変化させて来た(注1)。
IT向けの集積回路のインターフェースや、基本ソフトウエア(OS等)や、アプリケーションプログラムインターフェース(API)、アプリケーション開発ツール、CADツールなどでは、投資効率の点だけでなく、ユーザーの利便性やソフトウエアの価値の面からも「インターフェース仕様の収斂、投資先企業の収斂、事業体の収斂」を引き起こしやすかった。 そこで用いられるプログラムやコンテンツは、ユーザーにとっての資産であり、ユーザーはそのような資産の価値を維持するため、他の技術方式への変更を嫌うからである。 元々、コンテンツが流通するには、データフォーマットやインターフェース仕様が共通化されなくてはいけなかった。
水平分業型の生態系(エコシステム)
投資効率と利便性の最大化という市場圧力によって、ICT向けの集積回路産業は、特定分野に専業化した事業体(モノカルカルチャー的企業)からなる「水平分業型」の生態系(エコシステム)へと移行して来た。
「水平分業経済」は、まるで、1980年代末に崩壊したソビエト連邦の計画経済の発想(最適地における最適品生産)に似る。 当初、労働集約的であった製造や組立は東アジアや東南アジアに展開し、知識集約的なR&Dやソフトウエア開発は北米に集中した。
但し、ファブを持たない設計事業や、設計を持たないファウンドリにも難点はある。 分業企業間のコントロールは、エコシステム全体が信頼を寄せる優秀な「リーダー企業」による方針の統率が欠かせないからである。 「リーダー企業」、もしくは、「カリスマ的業界のリーダー」による各社間の生産計画や開発ロードマップのすり合わせがないと、事業間のWin-Winは構築できない。
その点、それぞれの分野で完全な独占が生じず、寡占の段階に留まったことは幸いでもあった。 弱肉強食の市場原理や進化論的な適応選別が働き、事業の効率や健全性を維持させる力を市場に残ったからである。 寡占状態とはいえ、複数企業の間に競争関係が残ったことで、金融市場を通じた投資家からの圧力や、購入側からの価格競争力の要求、製品市場を通じた消費者の製品選別も働いたと思われる。
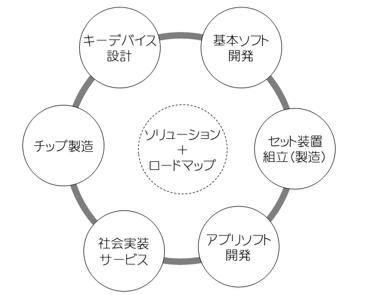
図1 水平分業体制(モノカルカルチャー的専業事業体) 連携が機能するには市場で優位性を保つソリューションとロードマップを維持する必要がある。 出典:筆者作成
リーダーシップと仕様書作成スキルの問題 : 日系企業の最弱点
水平分業が機能するには、誰かが各社間でソリューション仕様等の技術情報の開示し、開発ロードマップを提案し、業界を牽引する必要がある。 仕様の理解に齟齬(そご)があると、企業間で工程を進めることができなくなる。また、専業企業が互いの事業に挑戦しあうような事態は、分業体制の分裂を引き起こし得る。
Intel、Microsoft、Arm、Nvidia、Cisco Systems、Qualcommら、業界の名だたる半導体関連企業は、なぜ水平分業化に成功し、なぜ日系半導体企業は成功しなかったのだろうか?水平分業が機能するには、各社が敬意を持って受け入れ得る技術仕様や製品ロードマップを、説得力を持って提示し、業界を牽引しなくてはいけなかったはずだが、日系半導体企業の何が問題だったのだろうか?疑うべきは、投資方針、開発方針、教育、文化、人事等、多々ありうるが、筆者の経験にてその結論を言ってしまうと、問題は、業界を牽引するリーダーシップと仕様書の品質、およびそのような仕様書を整備し公開しようという事業戦略の欠如であったと思う(注2)。
リーダーシップに関しては、そもそも、日本人経営者が世界に報道され難いという事情もあるだろう。 しかし、そもそも、当時の日系企業の多くは受注型であり、「業界をリードしようとなど、思ってもいなかった」というのが正直な所であった。 事業方針が、市場と業界の状況を理解し、潮流に乗ろうという戦略や意志はなかったといえるのではないだろうか?下請け型IDM企業では、世界規模の競争にて望まれるコスト構造や技術提案ができるはずがなかった。
また、下請け型企業では、自ら仕様書を書く素養や社内文化が育まれない。「仕様書を書くスキルで劣る」との問題は、契約文書の作成能力とも共通し、グローバルな事業を進める際には非常に深刻な欠点であった。「仕様」それ自体は収益を生む訳ではないが、事業者間の準契約文書であり、産業エコシステムにとっての最重要な知的財産物であり、企業活動の基本である。 その認識が余りに乏しかったといえる(注3)。
この1年、新聞やテレビ報道にて日系半導体産業の再生議論を見ることがあるが、「企業の中に今も巣食うこれらの最弱点についての認識が余りに乏しい」と、筆者は思う。
モノカルカルチャー的事業のビジネスモデル: 消費電力の大きな集積回路商品の必要性
リーダーシップや仕様書の作成スキルの欠如という問題の次に、事業のビジネスモデルを問題としたい。 筆者は、以下を仮説として持っている。
「集積回路チップの利益率は、消費電力や搭載素子数と正の相関を持つ」
これは、「チップ統合を進めるべき」という意味ではない。 成功してきたビジネス例であるPCでは、何十年も部品点数は大きくは減っておらず、スマホでは部品点数がむしろ増えて来ている。また、売れないほどの大きなチップを作るべきだという意味でもない。 消費者や分業エコシステムが支持する商品は、性能を追及するゆえ、利益率が高いだろうとの意味である。
過去50年以上にわたるロジック集積回路の集積度アップの歴史は、必要な開発費用が幾何級数的に増える歴史でもあった。 定期的な微細化加工の進展は、搭載する回路数や素子数増を可能とし、必要な設計工数の増加を必要として来た。2021年までの50年間、民生用の高集積なロジックチップは、毎年約1.4倍、10年で約10倍のペースで素子数を増やしてきたが、ほぼ同じペースで開発費用も増やして来たはずである。 結果、面積が比較的大きく、集積度が高いチップが先行者利益を享受し、新規参入者への障壁を高めて来た。
利益率と消費電力や搭載素子数の間の正の相関は、現在、ますます明瞭になってきているとも思う。チップの利益率が高くないと企業は、仕様書作成作業や人材育成に費用を割くことができない。また、「性能」を競わない商品では、価格が最大の差別化要因となるので、キーデバイスとして認知され難い。性能限界にチャレンジする必要のない商品は、一般にはレッドオーシャンなビジネスだろう。
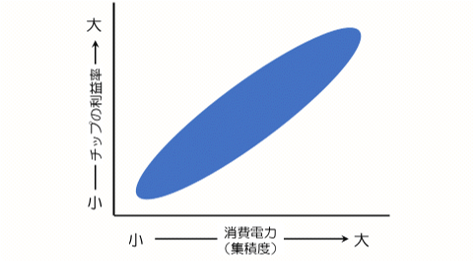
図2 チップに関する利益率と消費電力や集積度との間の一般的な関係 出典:筆者作成
業界のリーダーと名乗り出る経営者がIT系のロジック集積回路の分野で、「目指しているもの」を語るとすると、その「何か」は、現在の素子数や集積度では実現できないほどに大きな回路であり、まだ現状の製造技術や回路技術ではどうしてもチップ面積や消費電力が大きすぎ、未だ実現できない「何か」なはずだ。だからこそ、分業システムは、その実現に向けて位相を合わせた開発を進めることができる。
計算チップや通信チップのリーダー達は、ロードマップの先に、消費者が潜在的に求めるSF(サイエンスフィクション)のような装置向けのチップを語る。 単なる他チップとの統合ではなく、未来を感じさせるチップへの取り組みを語るのである(注4)。
データセンター向けやスマホ向けに、現在、巨大なチップ開発が進行しているのは、分業システムが、ロジック系集積回路の付加価値維持の現実論と人類史的な夢を共有するからである。 利益率と夢を追求することがエコシステムを束ね、エンジニアにモチベーションを与え、チップに価値を与える。 大きな目標とそのビジネスモデルを語るリーダーと、それを仕様化する開発者達の活躍なしに、分業エコシステムは成立しないと、筆者は思う。
また、余りに高くなってしまった「参入障壁」に向けて、後発企業にどのような戦略がありうるのか? その高さは、企業だけでなく、政策当局の側に関心を持ってもらうべき高さとなっているのではないかと、筆者は思う。
仕様化スキル + 政府や公的研究機関のサポート
1990年代後半、集中豪雨的な投資によってインターネットが敷設され各国の各種通信網は繋がり、電話、データ通信、放送の通信方式と、「通信仕様の収斂」に向けての各種インターフェース技術の標準化の時代が始まった。
通信設備は、民間企業の基幹インフラの一つであり、歴史的には各国、各社で仕様は異なっていたのだが、そこに、アダプターとなる変換回路を介在させて標準仕様にプロトコル変換すれば、異種の装置も相互接続可能となる。 「アダプター」は、ローカルな固有資産(プロプリエタリー)であるネットワークを、標準仕様を持つかのようにみせかける変換装置である。 アダプターが開発された結果、通信は、インターネット仕様に収斂し始めた(表1、注5)。
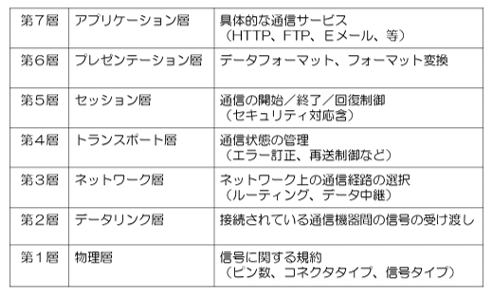
表1 ネットワークの階層構造に関するOSI(Open Systems Interconnection)の参照モデル 出典:ウィキペディア
更に、モバイル通信技術、Wi-Fi/LAN、TV、Bluetooth、USB等の通信インターフェース機能や、様々なファイルフォーマットやセキュリティ/認証プロトコルの標準化が進み、端末が用いる全てのファイルやコンテンツが、世界中を市場として転送可能となった。
コンピュータのCPU方式やOS(オペーレーティングシステム)の違いも、ミドルウエアやドライバソフトによって仕様を変換し、共通のアプケーション・ソフトウエア・インターフェース(API)への収斂を進めた。
「通信仕様の収斂」や「API仕様の収斂」は、アプリケーションソフトやコンテンツを装置間で共用可能とし、アプリケーションソフト市場やコンテンツ市場を拡大させ、ユーザーはより低価格にそれらを利用できるようになった。
これらの標準化も、市場の力による標準化である。 市場でヘゲモニーを持つ企業が推し進めるデファクト標準であり、市場に参加する企業間の合意による標準化ではない。 OSI の参照モデルは、オープンな仕様であるが、市場で優位にある企業の技術戦略であったため、市場での知名度を高めることで競争相手の開発意欲を打ち砕き、寡占状態をより確かにする巧みな戦略でもあった。
知財開発、標準化、寡占化が北米大陸で進み、製造はより安いコストを求めて東アジアや東南アジアに展開し、両者を結んだ水平分業体制による情報産業の大躍進の道という大きなトレンドがスタートした。 インターネットバブルと見なされた時期があったものの、そのトレンドはその後のGAFAの躍進に繋がった。
それら知財構築は、1980年代の米国のレーガン政権の大規模な規制緩和によって力を得たことは注目に値する。 技術の進化が引き起こす「必然」を捉えての、投資の促進、安価な製造体制の構築、分業体制構築に向けて、政府は規制を緩和し、市場の力を味方とするトレンドを作ったともいえるだろう。
経済学教授の荒井弘毅氏と林秀弥氏は、「1970年代後半から80年代にかけての米国内における反トラスト政策・競争政策の大きな変化は反トラスト革命(アンチトラスト・レボルーション)であったといわれ、情報通信・電力・航空・トラック運送業などの多くの産業分野において大規模な規制緩和となる独占禁止法の運用緩和が実現した」と説明している(参考資料8)。
市場の進化を捉えたビシネスモデル:メトカーフの法則
1980年代に、ロバート・メトカーフ氏は、「ネットワークに参加する装置数が増えてコミュニケーション可能な装置が増えると、装置1台の価値は接続可能な装置数に比例して増大する」との仮説を唱えた。これは、通信技術の価値を市場シェアの観点から捉えた表現であった(注6)。
この仮説を、1990年代に、ジョージ・ギルダー氏は、「ネットワーク全体の価値は、そこに接続可能な端末台数の2乗に比例する」というネットワーク・ビジネスモデルの表現に改めた。 以降、この表現が、メトカーフの法則と呼ばれることとなる(参考資料9)。
メトカーフの法則では、ネットワークの価値は、端末が普及する台数の2乗と見積もるため、端末の価格を下げてでも端末台数の普及を優先するとの事業プランが成り立ちうる。 その方が、トータル利益が大きくなるからである。
ネットワーク・ビジネスモデルは、現代の代表的ビジネスモデルであるが、今や集積回路事業も、そのようにビジネスモデルの観点からチップの価値を考えないと事業は成り立たない。 当然、日系の集積回路企業もビジネスモデルが問われているとの認識が必要である。
一定の投資金額の中で、優秀な人材を雇用し、ハードウエアのインターフェース仕様の標準化を進め、ソフトウエアやコンテンツの流通を拡大させる集積回路を普及させることを狙うには、チップや端末の製造コストが安価な「製造」が必要である。
実は、「製造」だけを考えると、製品の低価格化を引き起こす汎用化や標準化はレッドオーシャンでしかない。「製造」は、典型的な「規模の経済」であり、初期投資が最も大きな事業である。 1990年代は、まだ、労働集約的でもあった。
多くの北米企業が、「仕様」のオーナーとなる企業ポジションを獲得すべくファブレスの道を選び、製造投資は東アジアや東南アジアにて行われファウンドリ事業が躍進したが、その間にあった日系のIDMにて、企業のレベルでビジネスモデルを考えなかったのは悲劇であったと思う (注7)。
このことは、筆者が、本ブログにて、「集積回路設計事業」と「半導体製造」を分けて表現するよう心掛けている理由である。「半導体産業」と丸め込むことは、両事業のビジネスモデルの違いに由来する葛藤や矛盾を無視することになってしまう。 矛盾は、ビジネスモデルだけではなく、求める人材や、必要なマネジメント、必要な拠点のロケーションにおいても生じうる。
ネットワークビジネスを支える信用認証技術の収斂
ハードウエア仕様の標準化は、ソフトウエア開発者やコンテンツ制作者によっては朗報であった。装置が接続可能であるということは、OSIのモデル表現での第6層や第7層の標準化圧力ともなり、アプリケーションソフトウエアやコンテンツの市場を拡大する。 端末ユーザーが増え、多くの異種の計算機間もユーザーとなりうるようになったからである。
そのような事業環境にて、ソフトウエアやコンテンツの有料サービスや、個人情報が関与するデータの処理を行なうには、集積回路をデータセンターが認証し、更に、集積回路とそのオーナーの関係が紐付けされなくてはいけない。 その典型的なソリューションは、GSM Association、UMTS(日本でのW-CDMA)、国際電気通信連合 (ITU) が定めるIMT-2020、SIMカードやUIMカードの等に仕様化されてきているが、それらの本拠地は欧州にある。
データトランスフォーメーションが進む中、銀行業務も、行政も、オンライン化されたサービスに移行中であるが、「信用度の高いユーザー認証」をどこに求めてゆくかは、ネットワーク・ビジネスモデルの根幹であり、経済安全保障の一丁目、一里塚でもある。 しかしながら、日系の半導体企業からは戦略的な取り組みは乏しく、危機的な状況にあるように思われる。
更に続く収斂に向けて : まずは知財構築や人材育成に立ち戻った施策が必要と考える
「ネットワークの価値」や「集積回路の価格」が科学されてきており、その知見が現実のビジネスに反映されてきた。 そして、近年、集積回路のニーズは製造能力を超えるほどに力強く、市場拡大と開発投資の拡大の順回転は日々ニュースとして飛び交っている。
経済、人権、安全保障、国際紛争の面でもロジック集積回路の重要性は増しており、「シングルトン仮説(参考資料5)」や「ソフトウエア・アーキテクチャの収斂仮説(参考資料4)」に見られるように、人類史的なエポックとしても注目されるべき段階に突入しているとの認識もある。
にもかかわらず、論文や特許を検索する際、日系企業の名を見ることは、ますます稀となってきている。 日系IT企業や集積回路企業の市場ポジションの低下は明らかである。
少なくとも、集積回路に関しては、「弱点強化のための政府の助成」を戦略的に進めるとの発想が必要だろうと、筆者は思う。具体的には、アカデミズム/公的研究機関/大企業/スタートアップらの協調による、ビジネスモデル研究、集積回路の技術開発、仕様策定のトライアルの3点である。 それらによって、知財構築や人材育成を強化し、投資するに足る新たなソリューションとビジネスモデルとロードマップを構築する必要がある。
注釈
1. 水平分業体制の中で、モノカルチャーな分野での業界ポジションを競った時に、「設計」と「製造」のどちらへの投資を優先するかの判断が迫られ得るとすると、汎用メモリや画像センザのような特殊なボリューム事業を除いて、「設計」と「製造」の共存は困難と筆者は思う。
また、恐らく事業利益としては、北米企業の取り分の方が大きかったとはいえるだろうこの「棲み分け」が、今後どのように変わり得るのかは、今後の事業にとって重要な注目点となりうると思う。
2. この点に関しては、「日系企業が、モノカルチャー型になりきれないのは、卓越したリーダーに頼った経営ではなく、部門間の権力バランスの上で経営を進めるスタイルを取ってきたからではないだろうか?また、近年問題となってきている米中摩擦やTSMC問題は、製造系ファウンドリ企業と設計企業との間の「信用の危機」との面もあると筆者は考える。
3. PCや、サーバー、ルーターでは、キーデバイスの仕様書や、ソリューション説明文書は、産業エコシステム内の多くの企業への指示書のようなものであるし、開発ツールやユーザーマニュアルは、チップのユーザーの支持を受ける上で、最重要な提供情報である。 そのような情報と知財抜きには、水平分業は機能しないともいえるだろう。
仕様作成の能力やドキュメンテーションスキルの育成を、日系半導体企業の経営者は重視してこなかった。 投資家も政府の助成金も、未だにモノづくりによって成果物を提示することを重視しているおり、結果、日系半導体企業のエンジニアは、それらの分野に関して総じて弱い。それらは、非常に残念な時代錯誤であると思う。
4. 「究極のロジックチップ開発」は、より知的なチップの開発も視野においている。アラン・チュ−リングは、1950年の論文、“Computing Machinery and Intelligence”の中で、"Can machines think?”と問いかけた(参考資料7)が、現在の計算チップ開発と通信チップ開発のリーダー達は、ロードマップの先に、自律的に考える装置向けのチップを想定しているはずであり、他チップとの統合ではなく、自らが受けもつチップの性能向上にひた走っていると、筆者は想像する。
5. ここでのアダプター(Adapter)回路は、ラッパー(Wrapper)回路、デコレーター(Decorator)回路,メディエーター(Mediator)回路、デモジュレータ(Demodulator)回路などを含めた動作仕様の変換回路のことを言っている。
6. ロバート・メトカーフ氏は、1946年生まれの米国の電気工学者。 イーサネットの共同発明者であり、1979年に3-COM社を創業した。 イーサネットに関する メトカーフの法則は、当初1980年にユーザー数ではなく、ファックスや電話等の互換性ある装置を想定して提示され、インターネットの民間利用が始まり、この法則がユーザーとネットワークに適用されるようになった。現在の「メトカーフの法則」は、1993年にジョージ・ギルダー氏によって定式化されたと言われている(参考資料9)。
7. また、恐らく事業利益としては、北米企業の取り分の方が大きかったとはいえるだろうこの「棲み分け」が、今後どのように変わり得るのかは、今後の事業にとって重要な注目点となりうると思う。
参考資料
1. Gupta, S, Tyagi, T., "Convergence in ICT Industries: A Challenge for Competition Law Authorities", IIM Bangalore Research Paper No. 483, 2015.
2. C. Ebert, and A. Dubey, "Convergence of Enterprise IT and Embedded Systems", in IEEE Software, vol. 36, no. 3, pp. 92-97, May-June 2019.
3. Park, S. E., "Technological Convergence: Regulatory, Digital Privacy, and Data Security Issues", CRS reports (Library of Congress. Congressional Research Service), R45746, May 30, 2019.
4. Yampolskiy, R.V., "On the Limits of Recursively Self-Improving AGI.", in: Bieger J., Goertzel, B., Potapov, A. (eds) Artificial General Intelligence. AGI 2015. Lecture Notes in Computer Science, vol 9205. Springer, Cham.
5. Bostrom, N., "What is a Singleton? Linguistic and Philosophical Invest.", 2006 5(2): p. 48-54.
6. ウィキペディアの「自然独占」の項、2021年10月17日更新版。
7. Turing, A.M., "Computing Machinery and Intelligence", Mind, Volume LIX, Issue 236, Pages 433-460, October 1950.
8. 荒井弘毅、林秀弥著、「最近の企業結合規制の展開:米国の議論を中心に」、名古屋ロー・レビュー第2号 (2010/09)
9. ウィキペディアの「メトカーフの法則」の項。2021年7月19日の項。




