サイエンスのビジネスモデル化の時代へ突入、IBMのアライアンス戦略から
米IBM社Systems & Technology GroupのStrategic Alliances担当バイスプレジデントでありCTOでもあるBernard Meyerson氏(博士)は、半導体産業がビジネスモデルのサイエンス作りあるいはサイエンスのビジネスモデル作成の時代に入ったと、福岡県主催の「シリコンシーベルトサミット福岡2009」において明言した。これは技術の観点からさまざまな物理限界や経済限界をベースにしてIBMが打ち立てたコラボレーションのビジネスモデルを紹介したものである。
IBMはなぜアライアンスを形成、コンペティタとのコラボレーションを始めたのか。かつてトランジスタを発明したベル研究所はもはや存在しない。ジャック・キルビー氏はICを発明したが、すでに故人となった。エレクトロニクス、半導体産業はもはや、デバイスやハードウエアの発明の時代ではなく、ビジネスモデルのサイエンス化、あるいはサイエンスのビジネスモデル作りをしっかり行わなければならない時代に入ったと指摘する。なぜか。物理的限界、経済的限界が近づいてきたためである。これらの限界を突破するカギが積極的なコラボレーションになり、それに基づく競争になる。
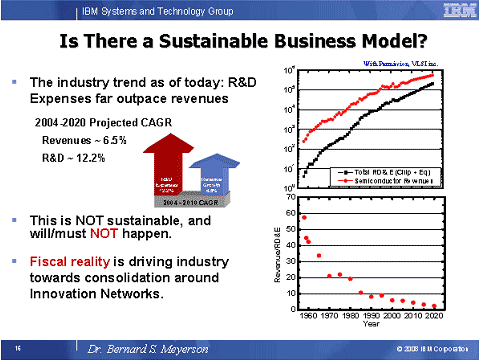
Meyerson氏によると、消費電力の問題はすでに1990年ごろに起きている。この時はバイポーラからCMOSへという流れに変わった。これはチップが発生する熱がアイロンの温度に匹敵するようになり、冷却ファンはヘリコプターのような動力が必要になったからだという。CMOSの後はどうなるか。今は低消費電力のマルチコア技術に移行しており、その先には3次元シリコンICが取って代られるだろうとしている。
では、デバイスだけを改良して済む問題か。今言われているグリーンITはサーバーやデータセンターで大量に消費する熱が問題としているが、プロセッサの熱を問題にしてプロセッサをマルチコアにすれば済むというものではない。実際に、データセンターで大量に使われる機器の冷却はIT機器の冷却が46%、データセンターの冷却が36%もあるが、IT機器の内訳は、サーバーが50%、ストレージが35%、ネットワーク機器が15%となっており、さらにHigh-kプロセスの導入による低消費電力の割合を分解していくとプロセッサは30%、メモリーが11%、PCIバス関係が3%などとなっており、High-kプロセスによる低消費電力化の効果はわずか0.3%にすぎないという。
ではデバイスをさらに微細化していくとその複雑さは極めて大きくなる。例えばリソグラフィでは、65nm~45nmだとマスクコストとOPCによる補正でパターンを作成できたが、32nm/28nmではさらにダブルパターニングなどの影響による補正も加わる。22nm以下はどうやってマスクを作るか。出来るだけ規則性のあるパターンにし、マスクと光源の両方を最適化の計算をする必要がある。この最適化のためにIBMの超高速スーパーコンピュータ、BlueGeneなどで計算し求める必要が出てくる。これは大変な作業になる。おまけにシリコンプロセスに使う材料の種類は周期律表にある元素の大半を使うように増えてくる。
IBMがAllianceを組んだのは、22nmの時代になってもMooreの法則の延長でCMOSトランジスタを使えるからである。このAllianceグループは、22nmのSRAMをSOIプロセスで試作している。SRAMはSoCやシステムLSIのレジスタ回路の基本となる要素であるためSRAMを試作したという意味は大きい。22nmまでは従来のCMOSスケーリング則の延長で行けるとしており、Mooreの法則の延長線上にあるとしている。しかし、それ以降はFINFETやETSOI、Siナノワイヤーなど、カーボンエレクトロニクスが登場するようになるかもしれない。
現実にカーボンナノワイヤー(CNT)は天の恵み(ボーナス)ともいえる素晴らしい特性を持つ。CNTを走る電子と正孔によりトランジスタが発光して遠赤外線を出すことがわかってきた。Light emitting single CNT transistorと呼び、光クロックを3次元ICとしてTSVではなく光配線でチップ間をつなぐということができるようになる。また、光トランジスタとして、光を電気バイアスのように印加しておき、入力に例えばデジタル信号を入れると光のデジタル信号が変調されて出てくるといった応用もありうる。
また配線技術では多孔質の自己形成ポリマーの膜特性を利用して、セルフアラインメント方式でエアギャップを作製するといった応用もある。あるいは。これらの技術を3次元的に積層して最上層に光トランジスタや光増幅器、変調器などを設ける3次元ICもあり得る。このようにして1チップ当たりのトランジスタ数を増やしていくMooreの法則を堅持できる。
ただし、このようなデバイス開発を進めるためには研究開発コストがかかりすぎる。2003年から2008年までに投資した研究開発経費は、IBM Allianceは500億ドル近い金額になった。しかし、企業単独ではこれほどまでのコストはかけられない。インテルでさえこの半分の額であるし、TSMCは1/3以下にすぎない。
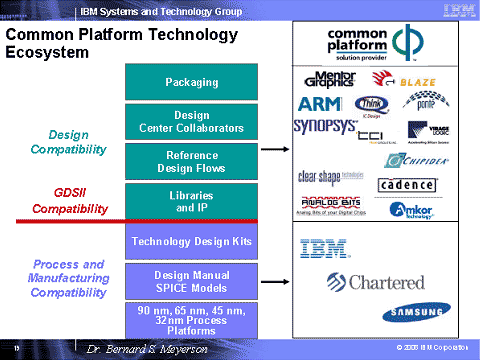
今後の研究開発にはもはやアライアンスは必要不可欠になる。というのはデバイス、プロセス、設計、IP、装置、材料、実装に渡るエコシステムが不可欠になり、必要な投資額はさらに増えるからだ。IBMのアライアンスは文字通りエコシステムが出来上がっているため、1社の開発負担は少なくて済む。
IBMの研究開発に対するコラボレーションは、基礎的なサイエンス部分のプリコンペティティブな領域に限っているが、企業によってはその部分が異なるため、各社とのコラボレーションのコスト分担は各社で違うとしている。設計からプロセスまでを見ると、差別化できるところは、やはりソフトウエアやサービスになるとしており、ハードウエアではRFやアナログが差別化できる技術であるため、これらの分野では決してコラボレーションしないと言いきる。IBM Allianceのビジネスモデルは、ハーバードビジネススクールの格好の教材となった、とMeyerson氏は結んだ。




