ARをIoTデータ可視化技術のインタフェースとするPTC ThingWorx
米Harvard UniversityのハーバードビジネススクールのMichael Porter(マイケル・ポーター)教授と3D-CADメーカーのPTCのCEOであるJames Heppelmann(ジム・ヘップルマン)氏は、デジタル時代のインタフェースは第4の波とも言うべき、AR(Augmented Reality:拡張現実)になるだろうと予測した。ARを使ったIoTデータの可視化は、IoTのソフトウエアプラットフォームである、PTC ThingWorxが得意とするところだ。

図1 Harvard大のMichael Porter教授(右)とPTCのJim Heppelmann CEO(中央)
3D-CADメーカーのPTCは、かつて2D-CADのPro Engineerから始まって、3D-CADのCreoへと名前を変え、モノづくりのPLM(Product Life-cycle Management)ソフトウエアのWindchill、さらにIoTのデータ収集・管理・分析・可視化用のソフトウエアプラットフォームである、PTC ThingWorxへと、モノづくりのデジタル化を支援してきた。IoTのセンサからのデータをクラウド上で取り扱い、ユーザーが可視化できるようなアプリを作成するソフトウエアプラットフォームが、PTC ThingWorxである。米半導体メーカーのAnalog DevicesやいくつかのデバイスメーカーがすでにThingWorxを使ってIoTデータを可視化している。
ThingWorxの特長の一つは、データ収集・管理・解析だけではなくARも使えること。例えば、工場の配管や、ポンプを引くモーターにIoTデバイスを設置し、モーターの振動や温度、配管に流れる流量などを常時測定していても、その測定値をすぐには見られないが、ARを使えばモーターや配管の映像と測定データを重ねてみることができる。ちょうど「ポケモンGo」のポケモンが映像画面に出てくるのと同じだ。
Porter教授は、コンピュータが誕生し、それまで紙や黒板で計算していたことをコンピュータ画面上で行うことができたことを紹介し、モノづくりの設計もかつては紙に設計図を書いていたが、やがてコンピュータ上で設計できるようにCADツールができたと説明する。ヒューマン-マシンインタフェースもコンピュータと共に変わってきた。昔のインタフェースは機械式にキーやつまみを回していた。コンピュータ時代には、2次元/3次元のアイコンやキーボード、スライダーなどタッチスクリーン上で操作するようになった。つまり、物理的なインタフェースが仮想的なデジタルインタフェースに変わった。
これからは、デジタルと物理を重ねて(融合させて)表示し、何が起きているのかをすぐに把握できるようになるとしている。人間は五感のセンサを持っているが情報の90%は目からの視覚によるところが多く、目で見て直感的にわかることが多い。デジタルと物理の融合という意味でARは第4の波と表現した。
ARは実際のビジネスでどの程度使えるものだろうか。CEOのJim Heppelmann氏は、107社にアンケート調査した結果、開発から製造ライン、物流、マーケティング、アフターサービス、人事などそれぞれにARが十数%は使えるという。例えば、開発だとデザインレビューに、製造ラインではオペレータへの指示などをARで表示できるという。
クルマの開発の例では、クルマのボディを3Dシミュレータで表現した後、そのデザインレビューにARを使う。フロントボディの流線形を修正したり、色を変えてみたりARを使いながら現実(物理)的なクルマに重ねて表示してみることができる。これによって開発期間を短縮できる。クルマの製造ラインでは、ある工程のマニュアルをARで表示し、ARに映った画面から仕様書を確認でき、作業効率を上げることができる。
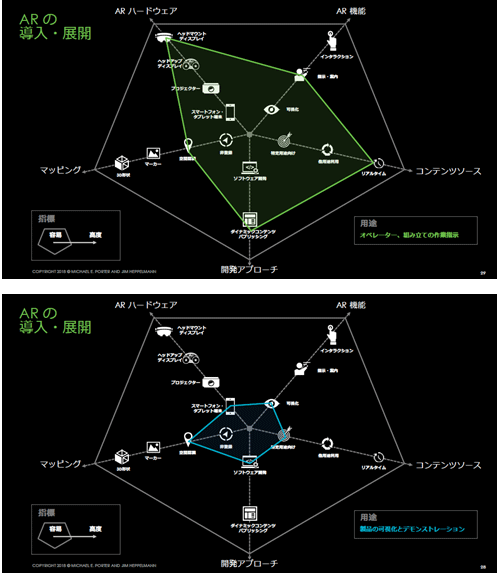
図2 ARを使った製品開発手法 オペレータの組み立て作業指示(上)と製品の可視化とデモンストレーション(下) 出典:PTC
Heppelmann氏は、ARによって、競争力のある差別化製品を生み出す手法も紹介した。ARを利用する製品開発の要素を5つに分解し、AR機能、コンテンツリソース、開発アプローチ、マッピング、ARハードウエアを頂点とするレーダーチャートを作った(図2)。例えばオペレータの組み立て作業指示の場合、AR機能は「指示・案内」、コンテンツソースは「リアルタイム」、開発アプローチは「ダイナミックコンテンツパブリッシング」、マッピングは「空間認識」、ARハードウエアは「ヘッドマウンドディスプレイ」として、それぞれを囲み一目で理解できるようにする。製品の可視化とデモンストレーションでは、AR機能は「可視化」、コンテンツソースは「特定用途向け」、開発アプローチは「ソフトウエア開発」、マッピングは「空間認識」、ARハードウエアは「スマートフォン・タブレット端末」を特長とした開発指針ができる。これによって、新製品開発の位置づけを知ることができるようになる
「自動運転を考えると、人間はもしカメが道路を横切ると何が通ったのかわからなくてもまずはブレーキをかける。マシンはどうするだろうか」と同氏は疑問を投げかけ、「ARは人間を助け、マシンとのバランスをとるだろう」と述べた。マシン偏重ではなくマシンが人間とほど良い関係を構築するのにARは使えるのではないだろうか。同氏は「ARはリアルタイムコーチである」と結んだ。




