半導体の市場規模、国・地域の拡大、そして三次元に拡がる技術
本年も残り僅か、クリスマス、お正月、そしてこんどは1月23日という旧正月と、世界各地でそれぞれの新たな年を迎える時節である。世界半導体市場も史上最高の昨年並み、あるいは若干越える販売高が見込まれているが、振り返って進展ぶりにいろいろ思いを馳せるのもこの時節であり、市場の規模、そしてグローバルな国・地域の拡大ぶりについて改めて自分なりの検証である。絶え間ない技術の前進が応用を拡げるエネルギーの源泉であることに変わりなく、現時点では三次元に拡がる流れが脈々と進んでいる。
≪流れのレビュー≫
半導体市場の変遷、変転をこの時節辿っていくのに格好の記事が目に入ってきて、次の通りである。1985年というと、小生にとっては最も前線にいて米欧を飛び回っていた頃になり、日米の半導体を巡る摩擦がピークを迎えていくタイミングである。
◇Tracking the Top 10 Semiconductor Sales Leaders Over 26 Years-Only Intel, TI, and Toshiba have been part of the Top 10 ranking since 1985 (12月12日付け IC Insights)
→半導体業界の変遷について定期的に見直して進展具合を辿るのは興味深いこと。1985年以降技術は素晴らしい早さで進んできているが、半導体を作るメーカーの名前および数も大きく変わってきている。1985年に販売高$2.1BでNECがNo.1となり、トップ10に日本メーカー4社が入っている。
1990年までに日本の半導体メーカーがトップ3を占め、No.1の座を保ったNECの販売高は$4.8Bと5年前の倍以上に達している。1990年にはトップ10に日本メーカーが6社、それ以降の国・地域別と合っていない図式である。・・・・・以降、経緯&変遷について。
・世界半導体ベンダーランキングの変遷:1985年〜2011年(見込み)
⇒http://www.icinsights.com/files/images/bulletin20111212fig.gif
この記事から1985年から現在までの半導体市場の規模、トップ10ベンダーの国・地域を見ていくと、次のように表わされる。
1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2006 | 2011予測 | |
| 半導体市場(B$) | 23.3 | 54.3 | 154 | 218.6 | 264.6 | 321.3 |
| トップ10ベンダー | ||||||
| 米国 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 日本 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 欧州 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 韓国 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| トップ10販売高 | 13.9 | 31.8 | 86.3 | 108.1 | 118.2 | 167.1 |
| (全体に占める比率) | (60%) | (59%) | (56%) | (49%) | (45%) | (52%) |
1985年当時からは約14倍の市場規模、トップ10ベンダーの方はいろいろ変化があって一概には言い難いが、ファウンドリーの台湾を加えて日米欧からアジア勢が加わる流れである。1995年がその境に感じるところがあるが、パソコンから携帯電話、そして通信ネットワークの普及拡大を経てconsumerエレクトロニクスと、それまでの産業・業務用から個人用途に拡大していって、市場規模が格段に拡がっていく流れを改めて受け止めている。
このような流れ、展開を支える力、エネルギーの源泉は、絶え間ない最先端技術の開拓、開発と、これは変わりなく思うところである。Mooreの法則を堅持していく頑固さは半導体業界に変わらず健在という基調は引き続いており、引っ張るインテル社からは三次元トランジスタ、FinFETが今後の軸としてすでに製品化ベースで発表されている通りである。本欄でも何回か触れていると思うが、同社はすでにその先を走らせているという記事が見られている。
◇Report: Intel has 14-nm process running in the lab (12月12日付け EE Times)
→Intel Northern Europeのmanaging director、Pat Bliemer氏にNordic Hardwareが行ったインタビュー記事。Intelが、22-nm製造プロセス技術の次の開発段階のものを同社laboratoriesで進めている旨。
このオーソドックスな微細化と並行して、半導体チップを三次元に積み重ねるアプローチが、等価的な微細化、そしてシステム性能の飛躍的向上を図る切り札として、これもすでに注目されてきているが、このところひとつ上の具体化を図る連携などの動きが相次いでいる。
◇ST-Ericsson describes three-chip stack (12月12日付け EE Times)
→ST-Ericssonとフランスのリサーチ機関が今週、Wide I/O DRAMなど3つのdieから成る半導体stackを発表、Cadence Design Systemsからのツールおよびメモリコントローラを使用、3つのデバイスstackの最初に数えられる旨。このstackは、シリアル非同期通信ネットワークを使用、1つの半導体上では550 MTransfers/second、半導体間では200 MT/sのスループットの旨。
3-D Architectures for Semiconductor Integration and Packaging(12月12-14日:Burlingame, CA)の場では、TSMCの独自な打ち上げが見られている。
◇TSMC goes it alone with 3-D IC process (12月13日付け EE Times)
→TSMCのsenior R&D director、Doug Chen-Hua Yu氏。TSMCは、integrated 3-D半導体stacking技術について今後の顧客に向けて同社唯一のofferingとして独力でやる旨。該アプローチは同社の営利的な捉え方であるが、それは技術的メリットに欠け選択肢が狭まるというファブレス半導体設計者の声がある旨。
◇Rambus, ITRI to collaborate on 3-D packaging (12月15日付け EE Times)
→技術licensor、Rambus社(Sunnyvale, Calif.)と台湾のIndustrial Technology Research Institute(ITRI)が、interconnectおよび3-D実装技術開発でコラボ、当初はSiインターポーザ技術によるシステムintegration開発に重点化、Rambusはまた、ITRIが主導するmultinationalリサーチassociation、Advanced Stacked-System Technology and Application Consortium(Ad-STAC)に参画する旨。
JEDECからもメモリとロジックのインタフェースについて踏み込んだ標準化提案が行われている。
◇First 3-D IC spec set for release (12月16日付け EE Times)
→2011年始めに3D IC標準開発の広範な一式を発表したJEDECが、初の3D ICインタフェース標準をリリースする運び、この12月後半か2012年1月に出される旨。今週始めのGSAの3D IC task group meetingにて、IntelのKen Shoemaker氏が、WideIO Memoriesのさらに詳細なプレゼン、電気的および機械的インタフェースが共有されている旨。関係図面、次の通り:
・WideIO Positioning
⇒http://www.eetimes.com/ContentEETimes/Images/08-16-11/MP_fig1.jpg
・logic to memory interface(LMI)インタフェースの詳細
⇒http://www.eetimes.com/ContentEETimes/Images/08-16-11/MP_fig2.jpg
・LMIインタフェースの機械的寸法
⇒http://www.eetimes.com/ContentEETimes/Images/08-16-11/MP%20fig3.png
・SamsungのWideIOインタフェースTSV-enabledモバイルDRAM
⇒http://www.eetimes.com/ContentEETimes/Images/08-16-11/samsung1.gif
来年、1年後にはこれら三次元アプローチはどのような進展となっているか、はたまた新たなキーワードが出現してくるか、兎にも角にも注目していくことと思う。
≪市場実態PickUp≫
現下の市場実態となると、欧米そして我が国の困難な環境が映し出されてくるが、半導体製造装置市場について来年は大きく減少する見方が出てきている。
【半導体製造装置市場】
◇Gartner sees 20% drop in IC capex in 2012 (12月14日付け EE Times)
→Gartner社(Stamford, Conn.)予測。2012年のグローバル半導体capital spendingが、大方はマクロ経済環境の鈍化から、本年見込まれる総計から19.5%低下すると見る旨。
2011年 2012年
13.7%増 19.5%減
$64.2B $51.7B
・世界半導体Capital Equipment Spending予測:2009-2015年
⇒http://www.eetimes.com/ContentEETimes/Images/111214_gartner_capex_423.png
半導体市場についても足元の鈍化が言われており、本年は$300 Billionの大台突破が見込まれて本欄でも取り上げてきているが、ここにきて暗雲気味の気配を感じるところである。底打ちの早からんことを願うのみである。
【現下の半導体市場】
◇Analyst says chip shipments near bottom (12月13日付け EE Times)
→Wall Street、FBR Capital Marketsのアナリスト、Craig Berger氏。半導体出荷が、今四半期後半あるいは2012年第一四半期始めに底を打つ様相、在庫削減がなくなっていって半導体出荷が消費水準に向けて戻していくと見る旨。
◇Analyst sees weaker chip sales in November (12月15日付け EE Times)
→Carnegie Group(Oslo, Norway)のアナリスト、Bruce Diesen氏。11月のグローバル半導体販売高・3ヶ月平均が、World Semiconductor Trade Statistics(WSTS) organizationによる10月の$25.74B並みの$25.6Bになる見込み、これからは実際の11月半導体販売高が前年同月比4%減となる旨。
これを考慮して、2011年グローバル半導体販売高はU.S.ドルベースで2010年(約$298B)と同じ、2012年は2%増、と見ている旨。
価格急落で困難を極めるDRAM市場について、以下のデータそして動きである。DRAMそしてNANDフラッシュと、最先端市場を切り開く最も基礎的なパラメータとして注目であり、絶え間ないブレイクスルーが上記のインテル社の動きと同様に問われているところと思う。
【DRAM市場】
◇IHS: Samsung grabbed record DRAM share in Q3 (12月12日付け EE Times)
→IHS iSuppli発。Samsung Electronics Co. Ltd.の第三四半期DRAM売上げが前四半期比8.9%減ったにも拘らず、市場シェアの方は45%と最高を記録、前四半期より3.5%拡大の旨。
・2011年第三四半期DRAM市場ランキングデータ
⇒http://www.eetimes.com/ContentEETimes/Images/111212_ihs_dram_423.png
◇DRAM vendors cutting capacity, says research firm (12月13日付け EE Times)
→TrendForceの市場リサーチ部門、DRAMeXchange発。DRAM価格急落の渦中、DRAMベンダーが、capacityを削減、あるいは製造capabilityをファウンドリーベースで他社に向けたウェーハ製造に充てている旨。4-GB DDR3 DRAMの契約価格が5月時点で$36.50、以降低下の流れとなって12月には$16.50と55%下がっている旨。
・DRAM wafer startの推移&予測: 2008〜2012年
⇒http://www.eetimes.com/ContentEETimes/Images/111213_dramexchange.png
厳しい状況の内容が続いたが、一転、月の表面でのコンペという壮大な闘いである。
【月でのコンペ】
◇Nvidia's Tegra 3 chip to be used in experimental moon rover (12月12日付け EE Times)
→$30MのGoogle Lunar X-Prizeに賭けるコンペで、Synergy Moonチームが、Nvidia社のモバイルTegraプラットフォーム半導体を用いる計画、該コンペは月の表面にロボットを無事着陸、500m移動して画像およびデータを地球に送り戻せることを競う旨。
≪グローバル雑学王−180≫
小学校の登下校を見守る緑のおじさん&おばさんが、我が国ではいつもの馴染みの光景であるが、いろいろな危険、リスクが潜んでいると知らされるニュースが途切れることはない感じがある。世界に広げていくと、さらに要因、種類、度合いが増すことを、
『こんなに厳しい!世界の校則』 (二宮 皓/監修:メディアファクトリー新書 029)
…2011年 6月30日 初版第1刷 発行
より以下の通り認識させられている。世界各地それぞれ、本当に学校に無事に辿り着く大変さを受け止めている。
第4章 登校
…朝6時55分に国歌斉唱! 学校に来るだけで大変なんです
□通学はリフレクターを着用すること(フィンランド 基礎学校)
・北極圏に近いフィンランド
→子どもたちにとって冬の通学は非常にdangerous
→登下校の必須アイテム、リフレクター(反射板)
・もう一つ、フィンランドの校則:
「通学タクシーの中では静かにして、運転士の指示に従うこと」(基礎学校)
→タクシーの利用も無料
□自転車、原動機つき自転車、小型オートバイ、スケートボード、キックボードで登校する生徒は、これらを指定の場所に駐輪し、学校敷地内で乗り回してはならない(ドイツ ギムナジウム)
・そんな乗り物で登校していいんだ、とストレートな驚き
→自己責任で通学しなさいとする学校側のスタンス
→かくも自由な通学スタイル
・ドイツの地方の電車やバスでは、自転車などの車内持ち込みが許可されているところが多い
□予防接種を受けた証明書がなければ学校に入ることはできない(アメリカ California州の規定)
・人種のサラダボウル、アメリカ
→アメリカでは予防接種が「義務化」
→生まれてすぐのB型肝炎から始まり、6才までに日本のほぼ倍の数の予防接種が義務
・本校則 →子どもを病気から守る正当な手段
・日本が基本的に1回に1種類の注射しか打たないのに対し、アメリカでは4、5本まとめて打つ
→子どもにとって非常にハードな一日
□場合によっては中学生にまで、登下校に親が付き添わなければならない(メキシコ 日本メキシコ学院)
・メキシコの私立学校において親の送迎は絶対
→富裕層の子どもは誘拐犯にとって格好のターゲット
→生徒を守るための重要な施策
・少なくとも日没以降は親の迎えが必須
・2部もしくは3部制を採用するメキシコの公立学校
→背景に人口の増加
→圧倒的に午前の部の人気が高く、出願日の初日には親が殺到
□教室内、27℃で猛暑休校(ドイツ ノルトライン=ヴェストファーレン州)
・ヨーロッパの夏
→2003年、2006年、2010年と記録的猛暑
→ドイツでは、一部の州の学校が具体的な猛暑対策
・ドイツの事情
→国民が基本的に暑さに慣れていない
→エアコンの普及率が圧倒的に低い
→<keller>と呼ばれる地下室に逃げ込む猛暑対策も
□週1回だけ学校に来ればよい(アメリカ California州ネトーマスチャータースクール)
・アメリカの義務教育、大多数の州で日本より2、3年長い
→学校が嫌いな子、勉強が嫌いな子を登校させる問題は、日本よりも深刻
・本校則のある「チャータースクール」…「charter」=特許状、認可状
→州や学区の教育委員会から特別に法令の適用外の許可を受け、自由な学校運営を可能にする制度
→全米に3000校を数え、70万人が学ぶ
→公立校と同様に公費で運営、絶えず一定の成果、つまり学力の向上が求められる
・本校則の学校には週に1度来るだけでいいという自学自習スタイル(independent study)の学科
・「ホームスクール(またはhome schooling)」
→自宅を拠点に学習。1回も登校しなくていい。
→150万人の児童がこのスタイルの学習(2008年、米国教育省)
→保護者が教師役を務めるのが基本
→支援する体制も充実 …「ホームスクール法律擁護協会(HSLDA)」
…「umbrella school」
□欠席の申請には充分な理由が必要。格安航空券を使うという理由は不充分である(ドイツ ギムナジウム)
・登校に厳格なドイツ
→「教育の義務」ではなく「就学の義務」を課している
→現行の学校教育を拒否する権利が認められていない
・本校則 →格安航空券だけでなく家族旅行そのものを欠席の理由として認めない
□毎朝、6時55分に国歌斉唱を行わなければならない(メキシコ 中学校ほか)
・通常、メキシコの中学校は朝7時から授業開始
→5分前の6時55分から、国旗を掲揚し、国歌斉唱をしなければならない
・国歌をBGMにした生徒行進も重要な学校行事の一つ
→敬礼のポーズ、メキシコ特有の作法
□校長と保護者の許可があれば、クルマで通学してもいい。ただし、学校の駐車場は使ってはならない(オーストラリア)
・オーストラリアでは17才から運転免許を取得可
・公の無料駐車場か路上のコインパーキングを利用するしか
・日本とは少々違う免許取得の流れ
→オーストラリア人も平均2回は不合格になっている模様
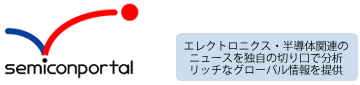
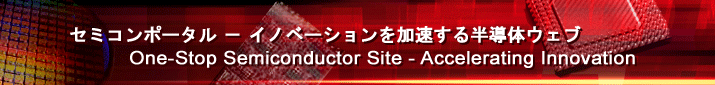

 半導体関連市場の動向
半導体関連市場の動向 技術コンテンツ
技術コンテンツ 経営・戦略ビジョン
経営・戦略ビジョン トピックス解析コラム
トピックス解析コラム 英国特集
英国特集 セミコンポータル編集長
セミコンポータル編集長 インサイダーズ
インサイダーズ インサイダーズ
インサイダーズ インサイダーズ
インサイダーズ インサイダーズ
インサイダーズ インサイダーズ
インサイダーズ インサイダーズ
インサイダーズ