自己放電少なく1万回の充放電サイクル可能な全固体Liイオン電池
厚さが1mmと薄く、リーク電流が従来のリチウムイオン電池の1/10、エネルギー密度がmA/cm2クラスの全固体リチウムイオン電池を英国のベンチャー、Ilika(イリカと発音)が開発した。ARMと同様、IPライセンスビジネスを主力に据え、量産パートナーを探している。

図1 Ilika社CEOのGraeme Purdy氏(左)とCSO(Chief Scientific Officer)のBrian Hayden氏(右)
液体の電解質を使わずに固体電解質を用いたのは、安全性が高いだけではない。自己放電が少なく寿命が長い、薄膜をベースにしているので体積が半分以下と小型・薄型化が可能になる。充放電可能な2次電池である。このほどライセンス可能なバッテリ技術を公開したのは商品名「Stereax M250」と呼ぶ、エネルギー250μAhのバッテリ技術である。
Liイオンセルは、充電時にLiイオンがカソードからアノードへ移動することによってLiイオンがアノード電極に潜り込む。放電時にはアノード電極に入っているLiイオンがカソードに移動する時に電子が外部に流れる。Li原子が蒸発などで失われないようにすることがLiイオン電池のカギとなる。
Ilikaが固体電解質の2次電池を開発できたのは、さまざまな材料の組み合わせ実験を1回で済ますことのできる化学材料開発手法、すなわちコンビナトリアル技術を持っているためである(参考資料1)。アノード(負極)にはアモーファスSi、カソード(正極)にはLiCoOを用いた。従来の全固体リチウムイオン電池では、アノードにLi3PO4(リン酸リチウム)を使っていたが、今回その材料を大きく変えた。アモーファスSiはLiPO電極と違い、カソードからたどり着いたLiが蒸発しにくいが、充放電サイクルが短い、という欠点があった。膜厚がバラつき、薄い所と厚い所が生じ、薄い所から壊れてしまったからだ。また、従来のLCOにはスッパタ後の800℃という高温処理が必要だった。アモーファスSiの欠点を克服するため均一な膜厚・膜質を形成することが求められる。均一な厚さに形成することは簡単ではないが、同社には秘策がある。
同社のコンビナトリアル技術に使うチャンバのEガンによる蒸着機がそれだ。従来のLiCoOカソードはスパッタリングで作られており、高温(800℃)でポストプロセス処理を行うと、Liが蒸発して抜けることが多かった。今回のアモーファスSiを使っているため、Liは蒸発しにくい。しかし、従来方法でアモーファスSiを形成しようとすると、均一な厚さを確保することが難しかった。今回はIn-Situモニタリング(チャンバ内で厚さをモニターする技術)しながら制御できるようにした、とHayden氏は語る。このため電解質も薄く形成でき、高いイオン電導度を得ることができたという。この結果、薄くて均一で、高品質なアモーファスSiと電解質薄膜を形成できるようになり、高い伝導度が得られるようになり、エネルギー密度も向上した。既存の固体電解質のバッテリよりも40%改善したという。
最初のライセンス可能な「Stereax M250」では、動作温度が-20℃〜100℃と広いうえに、260℃のハンダ温度にも耐えるとしている。今回の製品は1層のセルしかないが、これをスタックすることで電力を上げていくこともできる。多層に積む場合でも厚くならない(図2)。セルごとの封止膜が要らないからだ。また、Liの蒸発がないため、寿命が長いだけではなく、充放電サイクルも増えた。加速試験による充放電サイクルは1万回をクリアしたという。従来のLiイオン電池だとせいぜい1000回程度しかない。例えばスマートフォンは毎日充電するとしても1年で365回だから3年がせいぜいだが、1万回はその10倍の30年近くもつという意味である。だから「IoT端末やセンサ端末に応用できる」とPurdy氏は言う。
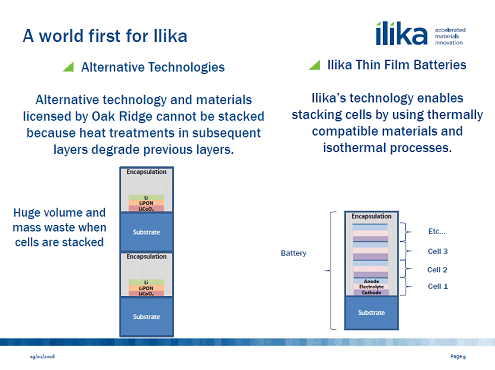
図2 セルを3個程度縦積みしても厚さは1セルとほとんど変わらない 出典:Ilika
今後のロードマップとして、3つの方向性があるとPurdy氏は語る。一つは従来の面積1cm2を1辺数mmとICチップ並みに集積できる大きさにすることだ。プロセスはCMOSと互換性があるため、RFを含むCMOS回路とバッテリ、ソーラーセルを一体化すれば、IoT端末として10年間メンテナンスフリーできることを狙っている。今回はガラス基板上にバッテリセルを形成したが、Siウェーハ上に作ることも考えている。
もう一つは大容量化だ。スタックすることで電力を稼ぐことができる。IoTセンサによっては、もっと大きな消費電力を必要とするものもある。
三つめは高温使用である。自動車向けには125℃まで上げたい。従来の電解液だとLiイオンが沸騰するため、使用温度を上げることはできなかったが、固体電解質ではそのような制限がないため、原理的には可能である。
同社は、研究開発企業であり、従業員のほとんどがPh D(博士号)を持つ。モノづくりはするが、量産はしない。このため、ビジネスモデルはIPビジネスのARMやImagination Technologiesと同様、ライセンス供与とロイヤルティ収入、サービス収入の3本立てを用意している。研究開発と量産をつなぐ技術を持つ日本企業とのパートナーシップを望んでいる。
参考資料
1. 新材料を短時間で開発できるコンビナトリアル手法で大きな前進 (2015/07/01)

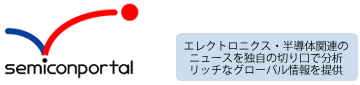


 インサイダーズ
インサイダーズ インサイダーズ
インサイダーズ インサイダーズ
インサイダーズ インサイダーズ
インサイダーズ インサイダーズ
インサイダーズ セミコンポータル編集長
セミコンポータル編集長 半導体関連市場の動向
半導体関連市場の動向 技術コンテンツ
技術コンテンツ 経営・戦略ビジョン
経営・戦略ビジョン トピックス解析コラム
トピックス解析コラム